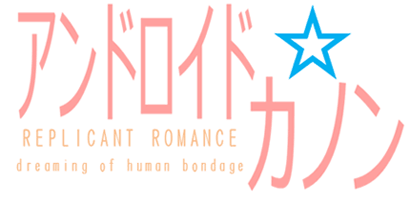
第弐話 KANON STRIKES!④
めぞんゴールドへの帰路、テラコッタ風の石畳が敷き詰められた十二宮ロードを意気揚々と闊歩するカノンは、いつになく上機嫌だった。カノンにとって、誰にも何も憚られることなく堂々と往来を歩くという行為は、実に奇跡的なことなのだ。対して、ミロは神妙な面持ちで、カノンの後を随分と遅れてついて行った。先行きのことを考えると、深刻にならずにはおられない。カノンが自らの支払いを一部負担したとしても、残金と維持費は少なからずミロの家計を圧迫するだろう。成り行きとはいえ、ミロにも契約主の矜持というものがあるのだ。
日は西へ傾きはじめ、時刻はそろそろ夕食時に差し掛かろうとする時分である。惣菜店の呼び込みが活気づき、フードコートエリアが賑わいを見せはじめていた。物思いから醒め、ミロがふと我に返ると、先を歩いていたはずのカノンの姿が見当たらない。慌てて周囲を見回すと、周囲より頭一つ分高い長髪が器用に人混みを潜り抜け、隣接するショッピングエリアへ消えていくところだった。良くも悪くも、カノンの姿形は遠目からでもよく目立つ。それにしても、人波を渡るにもすいすいと熟れた身のこなしだと、ミロは変なところで感心していた。
ミロがカノンに追いつく頃には、すでにレジでの会計が始まったところだった。そしてミロは、再び額に手を置くこととなる。百グラムにつき五百円のグリーンサラダ、一切れ四百円のキッシュ、一パック六個入りの卵が千二百円。見慣れない黒い瓶に入ったハチミツは、二百グラムで三千円もする。カノンが選んだ店は、輸入食材や直輸入ワイン、有名チーズなどを取りそろえた、高級プライベートブランドをもつ食品専門のスーパーマーケットだったのだ。
「五千五百八円になります」
ミロの二週間分の食費に匹敵する金額だ。懐から取り出した一万円札で、平然と支払いを済ませるカノンに、一体こいつはどういう金銭感覚をしているのだとミロはあきれた顔になった。
「おまえの部屋の冷蔵庫の中身は、空っぽだったからな」
レジの外でしかつめらしい顔をしているミロに、カノンはにやりと口の端をあげて笑いかけた。
「この俺の契約祝いだ。多少は奮発しても罰は当たるまい」
まったくこいつはいけしゃあしゃあと、と思いかけたミロだったが、結局口に出すのはやめた。よく考えてみれば、アンドロイドに食事が必要とは思えない。つまりこの買い物は、ミロのために、カノンが自発的に行動を起こした結果なのである。そう考えるとむやみにカノンを責めるわけにもいかず、仕方なく、ミロは無言でカノンから買い物袋を引き受けた。
二人の足取りは、帰り道でも対照的だった。鼻歌交じりのカノンと、押し黙ったミロ。カノンの金遣いは、今後一緒に生活していく以上、いずれ正してゆかねばなるまい。しかし、カノンの機転に助けられたのも事実である。さもなければ、ミロはサンクチュアリ社本社で、金がないから契約できない、と恥を忍んで告げねばならなかったのだ。
今日のところは、カノンには礼を言ってやらねばなるまい。意を決して、ミロの方から声をかけた。
「……お前、金を持っていたのだな」
「ん?」
訊ねられ、カノンは一瞬、何を言っているのかわからないという顔になった。
「馬鹿をいうな。俺はアンドロイドだぞ。そんなもの持っているわけがあるまい」
「……なに?」
「フッ、こんなこともあろうかと、お前の貯金を下ろしておいてやったのだ」
誇らしげに胸を張ったカノンは、ミロの気配が変わったことに、当然気づき損ねていた。ウワーッハハハハーーッと声高らかに笑うカノンの頭上に、昨夜から数えて三度目になるミロの鉄拳が振り下ろされるのは、この三秒後のことである。
「この、大馬鹿者があああああ!!!」
夕暮れ時の赤い空に、ミロの怒声が鳴り響いた。ちなみに、カノンがどのようにしてミロの口座番号やパスワードを知りえたのかというのは、いわゆる企業秘密というやつである。
*
サンクチュアリ社本社の上層階、それは一万人を超す社員から選び抜かれた一握りの幹部しか立ち入ることのできない、雲の上の場所だ。雲の上の中でも、ここはとりわけ天上に近い。なぜなら、サンクチュアリ社創始者・城戸光政の孫娘にして、現最高経営責任者・城戸沙織の執務室だからである。
『――これで手続きは終了だな?』
『契約完了です』
『というわけだ。おい、用が済んだらさっさと帰るぞ』
希臘町の全貌が見渡せるガラス張りの高層フロア一室。仕切りのない広々としたスペースの中央に設置された巨大な液晶モニターには、つい今し方まで階下で繰り広げられていた一部始終が、つぶさに映し出されていた。
意気揚々と外界へと飛び出していく一体のアンドロイドと、呆然とした面持ちで『彼』を見送る青年の後ろ姿で、守衛室から送られてきた映像はぷつりと途切れる。暗くなった画面の残像に、青年の豊かな巻き髪が跳ねるのを見て、ムウはかすかに同情を覚えた。
「『彼』が人間と契約を交わすのは――これが初めてですね」
黒いモニターをしばし見詰めてから、慎重に言葉を選んだムウですら、織り込まれた含みを完全に隠すことはできなかった。初めてどころではない。『彼』すなわち『カノン』が、誰かと契約を結ぶことがあり得たという事実、それこそが全く想定外で、非常事態なのだ。
「ええ! 今のところ、カノンはとても従順ですし、ミロも悪い人ではなさそうです」
従順……、と復唱しかけてムウはやめた。にこにこと上機嫌でモニターを眺めやる少女――城戸沙織の気持ちを尊重したからである。沙織は何事でもないかのように、いやむしろ、期待に胸を膨らませてでもいるかのような晴れやかな表情で、アームチェアから身を起こした。
「おじい様は、人間とアンドロイドの幸せを願っていました。アンドロイドは、いわばおじい様が残した未来の子どもたち。カノンとて例外ではありません。私はその遺志を受け継ぎ、両者にとってよりよい環境を築きたいのです」
沙織は感慨深げに微笑んだ。つられてムウも頬をゆるませる。彼女の言うことには、不思議と、内から自然に湧き出す説得力のようなものがあった。それがすなわち、多くの者が、彼女についてきた一番の理由でもある。実際に、沙織は信じているのだろう。人間とアンドロイドの幸せな未来を。たとえ道のりが、険しいものだとしても。
「貴女が留学からお帰りになって、社内の空気は変わりました。年若い貴女が重役に就くことをよく思わない輩もいたでしょう。しかし、貴女が戻られてからの五年間で、我が社のシェアは業界ナンバーワンに返り咲いた。今では、貴女の手腕を疑う者は、誰一人としておりません」
経営学のノウハウを、机上で学んだだけの年端もいかない少女が、大企業起死回生の策を講ずることができるなどと、当時の誰が考えたことだろう。
「みなさんの力添えあってのことです。それから、アンドロイドたちも」
この話になると、いつも控えめな笑みを浮かべるだけの沙織は、決して多くを語ろうとはしない。だがムウにはわかる。この少女は、周りが思う以上に稀有な能力を秘めた、紛れもないカリスマなのだ。
「お話中、失礼いたします」
品の良いインターホンのメロディが流れ、室内に女性の声が響いた。
「ポセイドン社からお荷物が届いております」
「贈答品は、秘書課で管理することになっているはずですが?」
丁寧ながらぴしゃりと反論を許さないムウの口調に、女性はたどたどしく口ごもった。秘書課に配属されて間もない新人なのだろう。
「はい……。ですが、ポセイドン社社長から、その、お嬢様への個人的な贈り物だと……」
「ジュリアン氏から私へ?」
「はい。そのように承っております」
沙織の声に勇気づけられ、女性の声が明るくなる。困ったような表情を見せてから、沙織は答えた。
「かまいません。お持ちなさい」
国内シェアにおいて、サンクチュアリ社に次ぐ地位を持つ大手通信事業者、ポセイドン社とは、同じアンドロイド市場をけん引する同士として、浅からぬ因縁がある。過去に幾度となくしのぎを削った間柄でもあったが、先ごろ、新社長にグループ御曹司のジュリアンが就任してから、関係は変わりつつあった。
しばらくして、匂い立つような大輪のカサブランカが室内に運び込まれてきた。凛として気品漂う高貴な姿は、どこか沙織を思わせる佇まいである。添えられたカードには、ジュリアン氏直筆と思われる伸びやかな筆跡で、Miss Saoriで始まるメッセージが綴られていた。
「ジュリアン氏は公明正大な方です。今のポセイドン社は、我が社のよきライバルであり、ビジネスパートナー。過去の確執は水に流し、友好的な関係を築きたいと願っています。私も、ジュリアン氏も」
心配そうなムウの視線の意味を先取って、沙織は微笑みかけた。確かにそうかもしれない。沙織がサンクチュアリ社を変えたように、ポセイドン社も若き御曹司によって改革の時を迎えているのだ。個人的な感情が若干、いや、多分に入っているにせよ。
十三年間絶縁状態だったポセイドン社との交流が回復したのは、ごく最近のことなのである。
「十三年」
ぽつりと零れ出た独り言は、ムウにしては珍しく失言の類いだったかもしれない。が、同時に言っておかねばならないことでもある。
沙織の愛は、アンドロイドと人間、すべてのものを包み込むほど大きくて深い。しかし、その彼女自身を守る盾と、理想を実現する剣もまた、必要なのだ。
「ジェミニモデルが目覚め、ポセイドン社は新社長の時代へと移りました。そしてもうひとつ、市場で気になる動きがあります」
「偶然ではない、と言いたいのですか?」
「いえ……」
ムウは短く答えた。瞬時に考えをめぐらす。仕組んでできるようなことではないのだ。これは。
「ですが、何かが動き出している兆候かもしれません」
カノンの契約主となったミロが、ムウの管理する住宅に入居していたのも、たまたまそうであったとしか言いようがない。それ故に、これらの偶然には、何か意味があるように思えてならなかった。
「十三年前の事件で失墜した我が社の信頼を、貴女は見事取り戻した」
沙織が、はっと息をのんだのがわかった。
「貴女がご存知ないのも無理はありません。まだ幼くていらしたのですから。ですが、我が社の存亡に関わる最大の危機を招いたあの事件は、深い傷痕を残しました。それは、ポセイドン社にとっても同じ」
「あれからもう十三年もの年月が経つのですよ……」
「まだ、十三年です」
ムウは若草色の瞳で、じっと沙織を見詰めた。
「ジェミニモデルは、存在を抹消された機体です。そのことを、お忘れになってはいけません。サンクチュアリ社総帥である、貴女ご自身は」
キュッと唇を引き結んだ沙織は、しばし押し黙った後、それでも、と言った。
「それでも、私は信じたいのです。より良き未来を」
ムウはそっと瞳を伏せて沈黙した。穏やかな表情を崩さず心の中で呟いた。貴女はそれで良いのです。だから、我々がいるのだ。アテナ・沙織の剣となり、盾となるために。
沙織は、花の芳香を楽しもうと、黒檀のデスクの上に活けられた豪華な花弁に、そっと頬を寄せた。