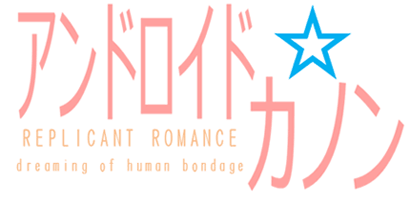
第弐話 KANON STRIKES!③
抜けるような青空と透き通った日差しは、レンガ造りの家壁や石畳をひときわ美しく映し出していた。歩道に立ち並ぶ街路樹が天に向かって長い枝を伸ばすさまは、この日の晴天を称えているようでもある。
道すがら、街路樹に交えて植え付けられたアーモンドの木の枝が、心地よい風に揺さぶられ、白い花びらをはらはらと散らせた。
「そういえば、契約には身分証が必要なのではないか」
カノンについて歩きながら、ミロはふと気がついた。メッセンジャーバッグの中にあるのは革の財布とパスケースのみ。しかも財布の中には当面必要な生活費しか入っていない。
「心配ない」
動じた様子もなく歩を進めるカノンに、ミロは不審な視線を送った。
「保険証は俺が預かった」
「何?」
「一応忠告しておくが、貴重品を一か所にまとめておくのは感心しないな。空き巣にでも入られたら一発でアウトだ」
カノンは悪びれもせず、どこからか取り出したミロの保険証をひらひらと振って見せた。
「しかも警備会社にも入っていない安アパートではな。いいか、金持ちの家だけが狙われると思ったら大間違いだぞ。貴重品というものは、」
直後、昨夜ぶりに、ミロの拳がカノンの頭に鋭くヒットした。ものすごい音がしたので、周囲を歩いていた人々が何事かと注視するが、ただならぬ二人の様子に恐れをなして、皆そそくさと目をそらす。誰しも面倒ごとには巻き込まれたくないものだ。
「余計な世話だ! 手癖の悪い奴だな!」
「この俺を二度も殴るだと……!?」
やはりカノンは根に持っていた。
「人の物を勝手に持ち出すな!」
カノンの手から保険証を取り返すと、ミロはさっさとバッグにしまい込んだ。
「俺はアンドロイドだ。契約主の個人情報は、把握する必要がある」
「いらんと言ったはずだ! 自分の面倒は自分でみられる。使用人など不要だ」
「使用人じゃないと何度言わせる気だ!? だいたい俺が持ち出さなければ、お前、身分証を家に置いてきたところだっただろうが。二度手間を省いてやったんだ。感謝されこそすれ、文句を言われる覚えはない!」
「そういうことは、まず俺に言えと言っているのだ!」
「今言った!」
「遅い!!」
カノンはちっと舌打ちした。自尊心ばかり馬鹿高いこの男は、とかく融通というものを知らないらしい。確かに勝手に持ち出したのは悪かったかもしれないが、結果、手間を省いてやったのだから、やはり感謝されたっていいはずだとカノンは思う。だが、これ以上どう都合よく見積もっても、ミロが褒めてくれそうな気配はこれっぽっちも漂っていなかった。
どうあってもミロをやり込めることはできないと観念し、カノンは口を噤んだ。カノンが静かになったのに呼応し、ミロも怒鳴るのをやめる。どちらからともなく歩きはじめると、残った方がそれに追従した。
「俺も、気づくのが遅れた」
しばらくして、ミロが前を向いたまま呟いた。カノンがさっと顔を上げる。
「そうだな」
その居直りのはやさは何だと、横からのミロの視線が語っていたが、カノンは無視した。保険証をとられたと気づくのが遅かったという意味にも聞こえるが、身分証が必要だろうということに考えが及ばなかった自分を省みての発言にも聞こえる。カノンは後者ととった。そうだ、やはり俺が機転を利かせて正解だろう。ミロもあえて触れようとはしない。
「……それと、財布の中身を勝手に見るな」
「なぜだ。ちなみに今月の支出合計は二万二千百四十円。残金は七千八百六十円」
「家計簿まで見たのか!?」
再びミロの眦が吊り上がる。
「昨夜一度だけ。一瞬で記憶できる。便利だろう」
得意げに言うカノンに、ミロは怒る気を殺がれ、ふうっと溜息をついた。家計簿の情報は、すでにカノンの中にインプット済みということらしい。今更言っても仕方のないことである。
希臘町の中心地は小高い丘になっており、町のシンボルでもある時計塔と、世界に名を轟かす通信事業者・サンクチュアリ社の本部が置かれている。これらの建造物を中央に据え、周辺には、雑貨店、飲食店に娯楽施設、人気ブランドの路面店から個人経営のファッションショップやギャラリーなど、さまざまな店舗が軒を連ねる。中でも、時計塔へと繋がる目抜き通りは十二宮ロードと呼ばれ、時間帯を問わず、買い物客で大層な賑わいをみせていた。
ミロたちが、十二宮ロードを抜けて空を見上げると、ちょうど時計塔が十一番目の火を灯したところだった。天高くそびえるこの巨大な時計塔は、数字の代わりに十二星座のシンボルマークが刻まれている。時計の短針があわさると、一時間に一度、火が灯るようになっているのだ。
火時計の火を見上げながら広場を囲む円形階段を上れば、そこには二本の支柱に挟まれた、サンクチュアリ社の正面エントランスが現れる。時計塔だけでも十分物珍しいのだが、サンクチュアリ社のオフィス外観も負けてはいない。エンタシス式の白い円柱が数十本も立ち並ぶパルテノン神殿のような建物は、それだけで見る者を威圧するし、エントランスへと続く石段を上りながら、破風に施された彫刻を見上げれば、いかな不心得者でも少なからず厳かな気持ちを抱くかもしれない。荘厳さと重厚さを醸し出すこのオフィスは、そうと知らずに訪れれば、世界遺産か美術館のようにも見えるだろう。いずれもサンクチュアリ社の前CEOによって建造されたものであるが、その所以を知る者は少ない。
長いコンパスを利用して、一段飛ばしで軽々とサンクチュアリ社本社入口の階段を駆け上がったカノンは、迷いのない足取りで堂々と乗り込んでいく。一方、階段を一段一段踏みしめて上ったミロは、呆れつつも、メッセンジャーバッグのストラップを絞め直した。これのどこがショップなのだ。
あっという間に回転扉の内側へと吸い込まれていったカノンの後を追い、ミロはエントランスに体を滑り込ませた。
吹き抜けのロビーに足を踏み入れると、正面には円形のドームがそびえ立っており、来客を取り囲むように、絵画や美術彫刻などが陳列されたギャラリーとなっている。厳めしい外観に劣らず、内装も古典的だ。
一足先にロビーに入ったはずのカノンの姿は見えず、かわりに来客の姿を認めた従業員のにこやかな笑顔が目に入る。従業員は、いらっしゃいませ、と丁寧に会釈をしてミロの方へ近寄ってきた。
「どんなご用件でしょうか?」
手続きに来たはいいが、肝心のカノンがいなくては話にならない。
「俺より先に連れが来ていたはずなんだが」
あいついったいどこに行ったのだと難しい顔を作るミロの心中を察してか、従業員は首をかしげ、申し訳なさそうに答えた。
「お客様のほかに、入っていらした方は見かけておりませんが……」
「そんなはずはない。今さっき、」
「本契約を結びたい。今すぐだ」
背後から唐突にカノンの声が聞こえ、ぐいと肩を押しやられる。従業員の前にずいと進み出たカノンは、用件のみを端的に告げた。
「おい、お前、どこへ行っていた」
「用を足してきた。それより、どうなんだ。ここの従業員は、契約にきた客を待たせる教育をされているのか?」
ミロに対してもさることながら、更に輪をかけて険のある態度を示すカノンに、ミロは眉をひそめる。
「お連れ様とはアンドロイドのことでしたか」
しかし、受付の従業員は気にした風もなく、カノンではなく、傍にいたミロに向かって深々と頭を下げた。
「承知しました。ありがとうございます」
カノンはあからさまに不愉快そうな表情を作る。カノンがどれだけ人間そっくりに見えても、左手首に光るバングルが、彼はアンドロイドなのだとその存在を主張しているのだ。
従業員が恭しく取り出したカードを乱暴にひったくると、カノンはロビーのさらに奥へと進んで行く。契約というから、てっきりパーティションか何かで区切られた対面式のカウンターを想像していたミロは、それらしきスペースがどこにもないことに、ここに来て気がついた。どれだけ見渡しても高級ホテルにありがちなラウンジソファとテーブルしか見当たらず、身の置き場もない。
「勝手にうろついていいのか。契約はどうする?」
「そのままお進みください。直進して左手にある白い扉の部屋へどうぞ。すぐに契約書類をお持ちします」
ミロの問いには従業員が答えた。カノンが手にしているのはカードキーの役割を果たすらしく、部屋の扉の前でかざすと、電子音とともにロックが外れる音がした。
室内は白と黒を基調にしたモノトーンな空間で、モダンなレザーソファとセンターテーブルが置かれている。カノンはソファに深く腰掛けると、ミロの部屋で窮屈そうにたたんでいた長い脚を悠然と組み替えた。この方が落ち着くとでも言いたげである。
ややあって、高級マンションのコンシェルジュよろしく、紺に青のラインが刺繍された制服を着こなしたスタッフが二人部屋に入ってきた。一人はテーブルの上に書類を並べ、もう一人はミネラルウォーターの入ったタンブラーグラスをミロの傍へ置く。
スタッフが保険証の控えを取る間に、ミロは契約書に必要事項の記入を済ませることにした。カノンが横から覗き込んでくる。
「めぞんゴールド八号……天蠍室? あのウサ」
「黙れ」
あのウサギ小屋にそんな大仰な名前をつけるとは、まったく大家の顔が見てみたいものだと、カノンが鼻を鳴らす間に、ミロは用紙の空欄をあらかた埋め終えた。電話番号なしではまずいということになり、仕方なく『めぞんゴールド』の代表電話番号を記入する。続いて、利用規約や注意事項で束になった書類を見やると、ミロはうんざりした声を上げた。
「一体何枚あるのだ。一つ一つ目を通していたら日が暮れてしまうぞ」
律儀に全ての項目に目を通そうとする人間なぞお前くらいだと、口に出さない代わりにカノンは呆れ顔になった。ミロが目線を上げたので、知らぬふりをする。ミロにとっても初めての手続きなので慎重なのだ。
「バージョンアップに関する同意……?」
「そこはサインしなくていい」
必要事項をすべて記入したことを確認して、カノンはミロから誓約書を取り上げた。
「必要かどうかは、俺自身が判断する」
パソコンの微々たる修正を更新するのにも、管理者の許可が必要な時代なのに、いくらアンドロイドが進化したからといって、そこまで任せていいものだろうか。思案顔のミロに、スタッフがうなずいてみせる。
「彼はそういうモデルなのです」
保証書もありますからご安心くださいと、銀のトレイに乗った黒い封筒を差し出されたミロは、中に入っていた請求書を見て驚愕の声を上げた。
「契約料、三十万だと……!?」
多少の出費は覚悟の上だったが、予想をはるかに上回る金額に、ミロは思わずスタッフとカノンの顔を見比べた。カノンはソファでくつろいだ姿勢のまま、動じた風もない。そしてなぜだか不服げである。一方、スタッフの方は、ミロが視線を向けると、驚くのも無理はないとでも言うように、神妙に頷いてみせた。
「性能は正規品とまったくかわりありませんから、ご心配には及びません。持ち込みでのご契約手数料は、通常の二割引で承っております。また、Proto-GEMINI0530は、」
「プロト……、なんだと?」
「Proto-GEMINI0530、彼のコードナンバーです。Proto-GEMINI0530は最終運用テストを省略したモデルですので、破格のディスカウントにより、大変お求めやすくなっているのです」
期待したのとは真逆方向の説明に、なるほど、どうやらこれがアンドロイドの相場であるらしいということは理解する。が、だからといって、そんな大金を容易く出せるかというとわけが違う。ミロのくたびれた革財布からは、表と裏をひっくり返して三度叩いてみたところで、到底出てきそうにない額なのだ。
「支払い方法はいかがされますか。クレジットカードもご利用いただけますが」
「キャッシュで」
カノンが即答したので、ミロは再び目を剥いた。ミロが言葉を発する前に、カノンは厚みのある封筒を懐中より取り出し、ぽんとテーブルの上に投げてよこした。唖然とするミロの目の前で、淡々と確認作業が行われる。封筒の中には、一万円札が三十枚、新札できっちりとそろえられていた。スタッフは、やはりミロに向かって、深々と頭を垂れた。
「確かに頂戴いたしました。残金は分割払いで、毎月利用料とあわせて請求させていただくようになります」
保険証が返却され、領収証が発行されるまでの一連の流れは実にスムーズだった。封筒と同じ、黒に金箔で押されたサンクチュアリ社のロゴ入りの手提げ袋に、大学の教材と同じ程度の厚みと重さを擁する書類一式を詰め込まれる。
「……残金とは?」
「アンドロイドは高額だからな。一括で払えるのは一部裕福層の人間だけだ。契約主のほとんどが分割払いを選択することになる。俺のような高性能モデルと一学生が契約できるなど、滅多にあることじゃない」
ソファに深々と腰掛け、優雅に足を組んだ余裕の様は、口を開いたときのカノンを知らなければ、どこぞのエリート実業家といわれても遜色ない。だからありがたく思えとでも言いたげなカノンに、ミロはもはや何を言う気にもならなかった。
「さて、これで手続きは終了だな?」
カノンのセリフには、間違いや否定を認めない圧倒的な圧がある。スタッフらは一瞬たじろぎを見せ、それから目配せしあうと、二人そろって首を縦に振った。
「契約完了です」
「というわけだ。おい、用が済んだらさっさと帰るぞ」
長居は無用とばかりに、カノンは素早く腰を上げた。特別にこの俺が荷物持ちをしてやろうと、渡された書類一式を軽々抱えて出て行ったカノンの背を、ミロは呆然と眺めるだけだ。ありがたみは、まったくもって感じられなかった。ともあれ、ミロとカノンの契約は、こうして晴れて完了したのである。