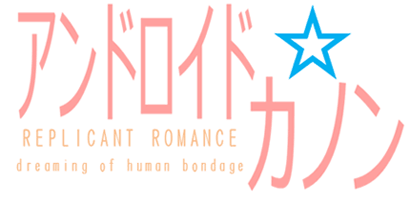
第弐話 KANON STRIKES!②
翌日は、晴天に恵まれた日曜日だった。ミロは言った通り、朝一でシャワーを使っている。扉が薄いせいで、水音どころか蛇口をひねる音すら筒抜けで、カノンはずっと落ち着かなかった。誰かと一緒に夜を過ごしたのも初めてなら、こんなにも長い間、自分の意思で誰かの傍にいることも初めてなのだ。
昨夜のレシートをもう一度見直そうとして、カノンは、傍にあった革の財布とパスケースに目を留めた。パスケースのクリア部分から学生証が確認できる。スターヒル大学とあった。ミロ。生年月日と資格取得月日とを照らし合わせ、現在二十歳で、三回生であることがわかる。
浴室の扉が開き、あたたかそうな湯気と石鹸の香りが漂ってきた。
ミロの態度が気に入らなくとも、今のカノンにとってミロは大事な契約主だ。ミロとの契約が破棄されれば、またいつ黒服たちが襲ってくるかもしれないのだ。
指紋登録をした時点では、本契約が完了したとは言えない。ミロ自身の個人情報や料金の支払い方法などを、最寄りの取扱いショップで登録しなければならないのだ。
「おい、出かけるぞ」
腰にタオルを巻いて長い髪をわしゃわしゃと拭いているミロの背に向けて、カノンは声をかけた。なんだ、とミロが軽く視線だけをよこして答える。そんなにごしごしこすっては髪が傷むんじゃないかと、もともとボリュームのあるミロの髪がさらに一回り膨らんでいるのを眺めながら、カノンは続けた。
「昨夜のは仮契約みたいなものだからな。正式には、ショップで契約をする必要がある」
「そういうものか」
昨夜の様子から、お前などいらんとミロが言い出した時のために、カノンが叩き出していた八十八のシュミレーションパターンが披露されることはなく、ミロはあっさりと答えた。
「だが、そんな店があったか」
「俺が案内する」
内心、拍子抜けしたものの、ならばこの仮契約主の気が変わらないうちに既成事実をつくってしまうにこしたことはない。カノンは即座に判断し、早いほうがいい、と言うが早いか立ち上がった。ショップまでのルートはすでに確認済みだ。
未だゆっくりと髪を拭いているミロに着替えを押し付け、ドライヤーを引っ張り出しては跳ねまわる巻き髪を落ち着かせ、朝はしっかり飯を食うものだと譲らない頑固者に、このすかすかの冷蔵庫の中身で何を言うと怒鳴りたいのを我慢して、ありあわせの朝食を供し、なんとか出立にこぎつけるまでの努力を尽くした自分を、カノンは褒めてやりたいと思った。我が身かわいさ故であることは、すっかり頭から抜け落ちている。
ちょっと待てと、ミロがややあわてた声を出したので、この期に及んでまだなにかあるのかと振り返ってみれば、ミロは昨夜のせんべい布団を縁側に出して、日光に当てているところだった。どれだけ日干ししようとも、カノンには、あの布団の寝心地が変わる日が来るとは思えなかった。
共同廊下に出て、通路を渡るあいだ、カノンは横目で表札を一つ一つ確認した。ミロの部屋は八号室で、隣は六号室。続いて四号室。どうやら奇数と偶数で部屋の並びが違うらしい。
「お、ミロか」
四号室の前を通りかかったタイミングで扉が開かれ、しわくちゃのタンクトップにスウェット姿の住人が顔を出した。たくわえた顎鬚をなでつつ、ニヤリと不敵な笑みを浮かべる男は、年若いがどこか老獪な雰囲気を醸し出している。
「タバコ買ってきてくれよ」
「自分で行け」
「愛想ねぇなあ」
ミロは近所付き合いに頓着しないたちらしい。相手の方も慣れているのか、特に気を悪くした様子はなかった。
「そいつは何だ? あの狭い部屋で同居人か」
「アンドロイドだ」
そっけなく言って、ミロはさっさと先に行ってしまった。取り残されたカノンと、男の目線とがかち合う。
「アンドロイドだって?」
「カノンだ」
「あっそ。俺はデスマスク。なあ、タバコ買ってきてくれよ」
「自分で行くんだな」
あ? とデスマスクが物騒な声を出したので、カノンは急ぐふりをしてミロの後を追った。共同玄関を出るあたりで、腕組みをしたミロがカノンを待ち受けていた。
「四号室のデスマスクだ。何を言われても放っておけ」
「了解」
カノンとしても、出会い頭にいきなり使い走りをさせるような相手と、親密なお付き合いをしたいとは思わないので、ここは素直に頷いておく。
「六号室のシャカとは基本絡むことはないだろう。他人に興味を示さない男だからな。二号室のアルデバランは気のいい奴だ。いずれ紹介してやる。それから――」
「おはよう、ミロ。朝からせわしないな」
陽の光を浴びて輝く植木の向こうから、薔薇の強い芳香とともに投げかけられた声音は、この上なく優美で物憂げだった。アパートの植木と混植されている草花に、薔薇の種類はない。だが、現れた麗人の繊手には、色も種類もさまざまな薔薇で作られたミニブーケが、確かに携えられている。
「アフロディーテ」
シルクレースのシャツに白のスラックスという、常人では到底着こなせないファッションを難なく纏う彼の名は、ギリシャ神話における愛と美の女神の名前らしい。その名にふさわしいたおやかな身のこなしは、青年の美しさをより一層際立たせていた。
「そちらこそ、休日の朝から庭の手入れか?」
「朝摘みの薔薇を、我らが管理人殿に届けようかと思い立ってね」
「家賃の滞納でもしているのか」
「デスマスクと一緒にするんじゃない」
淡々としているが、二人のあいだに流れる空気はどこか気安さを感じさせる。少なくとも、四号室の住人よりは良好な人間関係を築いているらしいと、カノンは理解した。
「アンドロイドのカノンだ。こちらは十二号室のアフロディーテ。ちょうど俺の部屋の真上にあたる」
「よろしく」
カノンの視線がミニブーケに注がれていることに気づくと、アフロディーテはこぼれるような笑みを浮かべた。
「敷地内の土地を借りて薔薇を育てているんだ。この奥にあるけど、見に来るかい?」
「悪いが後にしてくれ。これからこいつと、本契約とやらを結ばねばならんのだ。おい、行くぞ」
「俺に指図するな。ショップの場所もわからんくせに」
さんざん愚図愚図して時間を食ったのはミロの方だというのに、さもこちらが遅れているかのような物言いをされて、カノンは食ってかかる。
「案内すると言ったのはお前だろう。そもそも誰のためだと思っている」
「恩に着せる気か? この俺をあんな狭苦しい部屋に閉じ込めておいて」
「まあまあ、二人とも」
見るからに一触即発の雰囲気を呈してきた二人の間に、そつなく、しかしきっぱりと、アフロディーテは割って入った。
「あまり遅くなると時間が無くなってしまうよ。ほら、もう日も高い」
言いたいことはまだあると顔では語るミロだったが、素直に黙る辺り、やはりこの薔薇の守り人との関係は悪くないと見えた。カノンに余計なことを言い出す隙を与えず、バシッと背中をはたいて後押しする。麗しく見えても、アフロディーテは、芯の通った男なのだ。
「さぁ、行っておいで」
何だかんだ言いつつも、足並みをそろえて歩き出した二人の背中を見送りながら、アフロディーテは艶やかな唇の端をふと上げていた。この『めぞんゴールド』に吹き込んだ風が運ぶ、新しい季節を予感して。
「随分尖った気を感じたが、大丈夫なのかあいつら」
カノンとミロが去った後、ややあって植木の影から現れた男は、アフロディーテの華やかさとは対照的に、どことなく地味な出で立ちだった。すらりとした長身に切れ長の瞳を持つ彼は、十号室の住人で名をシュラという。表情に乏しく、いまいち感情を読み取りにくいが、鈍色に光る鋭い眼光からは只者ならざる雰囲気を醸し出している。抜身の刀、そんな表現がぴたりとくるような男だった。
「ミロの同居人か。あんなのでやっていけるのか」
「同居人じゃない、アンドロイド。……君、よく見ているようでいて、肝心なところを聞いてないな」
「アンドロイドとはなんだ」
ここにも一人時代錯誤がいた。
「携帯電話も持ったことがないミロが、いきなりアンドロイドとはね」
アフロディーテは、アンドロイドとは? から始まる、携帯電話の長くて面倒な歴史を説明する手間を華麗にスルーして続けた。
「美しいモデルだ。そうそうお目にかかれるものじゃない。ミロみたいな学生に、手が届くとは思えない」
「外見と価格が比例するのか」
「誰だって美しいものを傍に置きたいだろう?」
「そういうものか。何か訳ありなのかもしれんな」
分からないながら会話が成り立っているように見えるのが、このシュラという男の不思議なところだ。抜身の刀も、振るわなければ切れはしない。
「一体どこで見つけてきたのやら。……おっと、そろそろムウのところへ行かなければ。この後ブランチを一緒する予定なんだが、どうだい?」
「いただこう」
アフロディーテとシュラ、そして先に登場したデスマスクの間に友人関係が成り立っているという謎に、人間という生きものの妙をカノンが感じるようになるのは、もう少し先の話である。