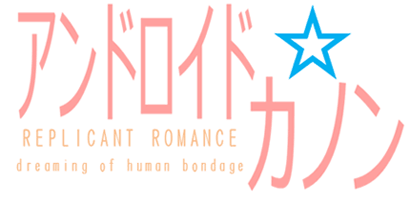
第弐話 KANON STRIKES!①
時刻は夜半をとうに過ぎていた。月が出ていないせいで黒く塗りつぶされていた夜空も、今は明け方が近いためか、春の星座に照らされ明るい群青色に染まっている。
ミロの住処は、背の低い街路樹が立ち並ぶ閑静な住宅地の一角にあった。木製の柵に囲まれた二階建ての集合住宅は、希臘町においては比較的珍しい木造建築である。広い敷地内には目隠しのため円錐型の植木が植え付けられており、一見すると手入れが行き届いているように見えるのだが、相当な築年数が経過しているらしく、塗装が剥がれかけた外壁には、伸びたツタが好き放題に模様を描いている。
極力音を立てぬよう、慎重に鍵を差し込んでからドアノブを回すミロの後ろ姿を、カノンは興味深く見守った。指先まで神経を張り巡らせるその姿は、カノンを背に庇い、黒服相手に啖呵を切って見せた姿から、あまりにもかけ離れていたからだ。
そうしてミロの肩越しに押し開かれた扉の向こうを覗き込み、カノンは絶句した。見渡すという表現では余る、狭くて小さな空間は、カノンがこれまでに見たどの部屋よりもコンパクトだった。仕切りがないため一目で把握できる全景は、天井が低く奥行きもない。
「ここは」
「声が大きい」
咎められても、カノンの声は上擦るばかりだった。時刻は夜更け過ぎだ。面倒ごとを避けるためにも、今は騒ぎ立てるべきではない。だが、ここが何のために作られた部屋なのか、持ちうる情報の中から一瞬で演算した結果を、カノンは確かめずにはいられなかった。
カノンが拳を握りしめる間にも、ミロはさっさと靴を脱ぎ、部屋の中へ上がり込んだ。部屋の中央から垂れ下がる紐をパチンと引っ張ると、室内に控えめな明かりが灯される。
「ドアを閉めてこちらへ来い」
促されても、カノンはそこから一歩も動こうとしなかった。
「ウサギ小屋だ」
「何?」
「ウサギ小屋だろう! お前、まさかこんなところに俺を押し込む気か!」
バン! と激しい音を響かせて扉が閉まるのと同時、カノンの頭上にミロの拳が思い切り振り下ろされた。
「で、どういう了見だ? 俺の家を動物小屋と一緒にするとは」
本当にそう見えたのだから仕方がないだろうと、激しい衝撃で未だくらくらする頭部を垂らして、カノンはたたまれた己の膝とその上の拳と、ところどころが毛羽立った畳の目を見詰め、心の中で毒づいていた。口に出さなかったのは、仁王立ちのミロの剣幕に気圧されたからではない。断じてない。これ以上言うと面倒なことになりそうだから、敢えて引いてやったまでだ。戦略的撤退だ。だいたい精密機械であるアンドロイドの頭部をぐーで殴るなど正気の沙汰ではない。壊れでもしたらどうしてくれる。これだから野蛮人は。情弱が。だいたい、それならそうと最初から言えばいいものを、説明を怠るからこうなるのだ。騒がしいのはどっちだ。カノンは己の失言にはさっぱり目を瞑ってまくしたてた。ちなみにすべて心の声である。
こぢんまりとした部屋のほぼ半分のスペースは、小さな木製の円卓に占拠されていた。円卓の一方には、腕組みをした部屋のあるじが、向かい側に正座する一応客を、剣呑な目つきで見下ろしている。
靴を脱いで上がるタイプの部屋、いわゆる和室と呼ばれる空間を実際に目にするのは、カノンにとって初めてだった。乾いた藁のような香りは独特だが、どこか気分を落ち着かせ、嫌な感じはしない。なのに、これが日本家屋というやつかと感動する暇など与えられずに現状である。情緒の欠片もない男だと恨み言を唱えながら、カノンは伏せた目を少しばかり上げ、そろそろと周囲を見渡した。
目につく限り、家具らしい家具は、本棚と衣装用の小さなチェストのみだった。ミロの胸に届くくらいの高さの本棚は、背表紙のある本で隙間なく埋め尽くされている。読書用とは明らかに異なる学術専門書が大半を占めていて、どうやらミロは学生らしいと、カノンは理解する。
カノンの殊勝(そう)な態度に怒りも鎮まったのか、ミロは、カノンの正面に腰を下ろした。円卓の上に置かれた雑誌を片し、手際よく折り畳んで壁にたてかける。それから、すっとカノンの方に向き直った。不貞腐れていたカノンもつられて視線を上げ、丸めていた背を思わず正す。凛とした気配に、堂々と胸を張る姿。無言で座する様は、無駄に姿勢が良い。真正面から見詰められると、それだけで背筋がぴんと張り詰める気がした。行儀の良さは、育ちの良さでもある。そういえば、ミロの一貫した命令口調は、確かに偉そうではあるのだが、その手のことに人一倍敏感なカノンでも、蔑みや嘲りといったものを感じたことは一度もなかった。ミロにとって、相手を馬鹿にする意図は微塵もなく、単に己への自信の表れなのかもしないと、カノンが思いかけていた時、ミロが口を開いた。
「俺は今まで携帯電話を持ったことがない」
「アンドロイドだ」
「似たようなものだろう」
見直しかけた評価を即座に撤回し、カノンは天を仰ぎたくなった。このご時世に携帯電話とアンドロイドを同列に扱う人間がいることにも驚きだが、これからその考えを正すために弁を振るわねばならないと思うとうんざりしたのだ。取説を読み上げるのとはわけが違う。
カノンの頭上には、今は月でも星でも太陽でもなく、レトロな傘つき蛍光灯から吊り下がった紐が、所在なさげにゆらゆらと揺れていた。
ひと昔前の携帯電話では、待ち受け画面で着信やメール受信、交通情報やおすすめスポット、災害警報やニュース速報などの情報を通知するキャラクターが登場した。中には音声機能付きのものもあり、質問すると答えてくれたり、ときには冗談を言ったりする。それがあまりにも自然で、人間くさくて面白いと話題になり、当時の一世を風靡した。
やがて時は流れ、画面の中で動き回るだけの存在だったキャラクターは、現実世界において、人間の直接的なサポートが行えるよう等身大のサイズになった。人工知能や人間工学など、科学技術の目覚ましい進歩により、自ら状況判断して行動し、持ち主の意に沿い、感情すら自らの意志で選び取ることができるようになるまで進化した。アンドロイドとは、老若男女の話し相手はもちろんのこと、買い物や料理、洗濯、掃除までもすすんでやる、いわば人型のスーパーコンピューターなのである。
ひと息に説明してみせてから、カノンはあらためてミロの顔を見た。専門用語は使わず、要点のみをわかりやすく説明したつもりだが、携帯電話も持ったことがないという相手に、いったいどこまで理解できただろうか。
「つまり使用人ということか」
「違う」
即座に否定したカノンだが、ミロの言うことはあながち的外れというわけでもない。契約主次第では、ハウスキーパーのような仕事をさせられるアンドロイドも少なくないし、人間のベビーシッターよりもアンドロイドの方がよほど優秀だという話も聞く。むろん、そんなふうに働かされるのなんてカノンはまっぴらごめんだが。
「使用人なら必要ない。自分の面倒は自分で見る」
「俺の話を聞いているのか!?」
「ではどう違うのだ」
至極真っ当な様子で訊ねられ、カノンは思わず言葉に詰まってしまった。揶揄や挑発には慣れているが、ミロのセリフにはそういった意図がまったくない。だから何となくいつもの調子で返せないのだ。
「電話は管理人室に行けば置いてあるし、交通情報も駅まで出ればだいたいわかる。そもそも俺は自転車通学だ」
「とんでもないアナログだな」
「それで事足りている」
拾われたと思ったら、即要らないと切り捨てられたも同然である。科学の粋を結集させて作られたアンドロイドが、携帯電話もろくに使ったことのない相手に、存在を全否定されたのだ。アンドロイドの機能を知れば、さしものミロも感嘆の声を上げるに違いないと疑いもしなかったカノンは、完全に勢いをくじかれてしまった。
ならばなぜ俺と契約した。訊ねるのも癪だが、他に言いようがない。カノンが次のセリフを探すあいだ、ミロは財布から紙切れを取り出して、畳の上に並べていく。スーパーや書店、コンビニエンスストアのレシート、電子マネーのチャージ証書まで、こまごました領収書の類いだった。どこからか出したノートを広げ、ボールペンを取り出すと、カノンの視線に気づいたらしく、ミロは平然としてこう言った。
「家計簿につける」
真面目か。
カノンは思わず突っ込みそうになった。今どきノートに家計簿をつける学生など、絶滅危惧種ではなかろうか。主婦でもアプリを使う時代だというのに。だが、ミロは大真面目な様子で、記入済みレシートの合計金額をマルで囲んでいる。
「そういえばこんな機能もある」
当然ながら、アンドロイドには計算機や家計簿の機能も備わっている。レシートを取り上げたカノンが、費目ごとに暗算した結果を伝えると、ミロは初めて感嘆の声を上げた。
「便利だな」
「そうだろう」
カノンとて、褒められれば悪い気はしない。ミロのような男には、あれこれとうんちくを垂れるより実践してみせた方が早い。
「辞書や翻訳機能もあるぞ」
得意になったカノンが、続けて需要のありそうな機能を披露しようとした矢先、ミロは突然すっくと立ち上がった。今度は何だと身構えたカノンをよそに、ミロはノートとレシートを整理すると、壁に備え付けられた引き戸を引いて、中からくったりとした白いマットレスを引っ張り出した。白いシーツと一緒に、畳の上へぼすんと放り投げる。
「続きは明日にしろ。今日はもう寝る」
ここで寝る気か! これからというところで出鼻をくじかれた感もさることながら、居間と寝室が一緒だという事実に、カノンは衝撃を受けた。そういえば、ベッドルームらしきものは見当たらない。狭い和室はマットレスを一枚敷いただけで手狭になってしまう。思わず横に退いたカノンは、居場所を探して室内を見回した。だが、男一人が足を投げ出してくつろげるようなスペースを確保できるはずもなかった。
ミロは脱いだ服を部屋の隅にあるバスケットに放り込んだ。洗濯所は部屋の外にあるという。カノンは首を傾げた。この家は屋外で服を洗うらしい。
「今日は、色々ありすぎた。風呂は朝一にする」
カノンに背を向け、ブランケットを広げると、ミロはくたくたマットレスの上に寝転がった。人差し指だけをのぞかせて、天井を指し示す。明かりを消せということらしい。
小間使いのような扱いが気に障る。それにあんなにも平べったいものの上で、十分な休息が取れるのだろうかということも、カノンには気がかりだった。カノンの知る限り、寝具とは、厚みがあってふかふかであるべきものなのだ。
「俺は?」
「お前、電話だろう」
「アンドロイドだ」
略すならせめて携帯の方にしろ、という突っ込みは不本意ながら胸にしまう。今の論点はそこではない。
「俺にその辺で雑魚寝しろと?」
ミロからの返事はない。
「冗談じゃない。俺をその辺のアンドロイドと一緒にするな。わかっていないようだからもう一度言っておくが、……おい、聞いているのか!」
「…………」
カノンの抗議の前にもミロはピクリとも動かず、静かに肩を上下させているだけだった。様子がおかしいことに気づいたカノンは、おそるおそるミロの顔を覗き込んだ。
――早過ぎやしないか? ミロは、既にすやすやと安らかな寝息をたてていた。何をがなり立てても、到底起きそうにない。それ以上言及するのは無駄だと諦め、カノンは仕方なく天井から吊る下がった明かりの紐を引っ張った。パチンとどこか懐かしい音と共に、ようやく室内に闇が落ちる。
暗闇の中、小さな息の音だけが聞こえる小さな空間で、カノンは今日のことを反芻していた。ごろりと畳に身体を横たえると、どっと疲れが襲ってくる。厳密には、アンドロイドに疲労という概念はない。だが、フル回転していたメモリーが速度を緩め、溜め込んだ熱量を放出していくのを感じていた。ミロの言うとおりだ。色々なことがいっぺんに起こり、事態はまるで予期せぬ方向へ転がっていって、今もきっと転がり続けている。思い返せば、カノンが目覚めてから、まだ数時間と経っていないのだ。
三秒で寝たミロとは対照的に、夜明けまでの三時間を、カノンは部屋の隅で、壁に背を預けて過ごすことになった。長かった夜が、明けようとしていた。