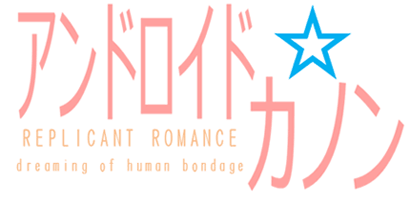
第一話 そのアンドロイド、不良につき③
カノンはずっと一人だった。寂しいとか、不便だと感じたことはない。それが常であったし、また必要も感じなかった。容姿や物珍しさに惹かれ、すり寄ってくる相手には、いつも一目で嘘が透けて見えた。
変わっている、他と違うと指摘されても、カノンは気にもとめなかった。俺のことは俺自身が一番よくわかっている。他人の評価など無意味なだけだ。自分で定め、認めた価値を、他の誰にも貶めさせはしない。
そんなカノンであったから、出会ったばかりの何も知らない青年を謀ることに、躊躇も罪悪も当然なかった。最初から、都合のいい人質として利用してやろうと思って連れてきたのだ。
だから今、向けられた銃口から、この身を庇うように広げられた両腕が何を意味しているのか、カノンはすぐに理解できなかった。
「何のつもりだ」
眼前で、癖の強い金の巻き毛が躍る。たった今銃弾の盾にされようとしていた人質が、自らの意思で立ち向かってきたことに、黒服たちは戸惑いを隠せない。
「それはこちらの台詞だ」
銃口を前にしても、人質――ミロに怯む様子は少しもなかった。
「そんな物騒なものを突きつけて、相手を思い通りにしようだなどと、どちらが悪者か一目瞭然ではないか」
耳に心地よい、少し高めのバリトンと、凜とした真っ直ぐな背中からは、顔が見えずとも、決然たる意思が感じられる。
「部外者は黙っていろ! 怪我をすることになるぞ」
「離れなさい。そいつは君が思っている以上に危険な存在だ」
苛立たしげな怒声にも、諭すような声音にも――引き金を絞る音にさえ、ミロは一歩も退かなかった。カノンは息を呑んだ。まさか撃つ気か。それとも俺への牽制か。だが逆上させれば、連中とて何をするか分からない。『こいつ』は、撃たれれば死ぬかもしれないのだ。
青年をその銃口の面に曝していたのは己自身であるというのも忘れ、カノンは咄嗟に、ミロの肩に手を置いた。毅然とした背中は、やはりびくともしなかった。
「丸腰の人間を、よってたかって拳銃で脅すような連中のいうことが聞けるものか」
消耗しているとはいえ、カノンと青年との力の差は歴然で、無理を通せば彼をその場から押し退けることもできたはずだ。けれどできなかった。カノンは不覚にも、この行きずりで出会った一青年に気圧されている自分に気がついた。
「人間?」
人を小馬鹿にしたようなせせら笑いが、一瞬で空気を淀ませる。カノンは、己の身がギシリと音を立てて竦むのを感じた。親愛から侮蔑へと堕ちる眼差し、裏切られたと浴びせられる罵声を、カノンは瞬時に思い出した。何もこれが初めてではない。何度もその瞬間を経験してきた。だが、なぜか今だけは、その先に続く言葉に、カノンははっきりと強い恐れを抱いていた。
「それは人間ではない――」
まるで断罪の宣告のように。
「アンドロイドだ」
重くカノンの上に落ちた。
銃口を向けられても微動だにしなかったミロの背が、わずかばかり強張った。広げていた両腕を下ろし、ゆっくりと、とてもゆっくりと、カノンを振り返る。
無言のまま振り仰ぐ青い瞳に、カノンは戸惑いを覚えた。そこには驚愕の色も、優越も落胆も嫌悪も、これまで見慣れたどんな色も映し出されてはいない。騙したのかと、いっそ詰られたなら、どんな切り返しもできるのに。
物言わぬ眼差しを正面から受け止めることが何となく躊躇われ、カノンはついと目を逸らした。ミロは何も言わず、そして、振り向いた時と同じように、ゆったりとした動作で黒服たちに向き直った。
「それが何だ」
カノンは自分の耳を疑った。伏せていた目を思わず上げる。ミロの真っ直ぐな背中は、変わらずそこにあった。
驚いたのはカノンばかりではない。黒服たちがざわめき立つ。
「アンドロイドだろうと人間だろうと、こいつは俺が拾ったものだ」
宣言して、ミロは素早く振り返り、カノンを見た。
「おい。手を出せ」
言うが早いか、唖然とする周囲の視線をものともせず、ミロはカノンの腕を取り、左手首のバングルに迷わず触れた。指先がバングルに浮かび上がった文字を確かめるように辿る。カノンは思わずその手を払い除けた。
『指紋認証を確認。仮登録完了しました』
機械音声が硬質な響きとともに告げる。そこに至り、カノンはようやくミロの意図を理解した。
「君……! 自分が何をしたかわかっているのか!?」
「契約した」
表情も変えず、淡々と告げるミロの顔を、カノンはただ見つめることしかできない。
「こいつは今から俺のものだ」
誰が、何だって? 一瞬、頭の中が疑問符で埋め尽くされたせいで、カノンは言葉を失った。こんなふうに処理能力が追いつかなかったことなど、今までに一度もない。カノンにしてみれば青天の霹靂だ。
「何を勝手なことを!」
「どうかしている。こんな事態は想定外だ」
黒服たちの喚く声に、カノンは、生まれて初めて同意してやってもいいとすら思った。何もかもめちゃくちゃだ。青年の言っていることは。勝手に人を所有物扱いして――それ以前に、あんなにも契約を拒んでいたくせに、いったいどういう風の吹き回しだろうか。
黒服たちの台詞など雑言とばかりに聞き流し、ミロはきっぱりと告げた。
「だから、こいつがこれまでしたことのけじめは、俺がつける」
ミロの言葉が理解という回路を通過するより前に、鈍い音と共に鋭い痛みが、カノンの右の脇腹を貫く。突如重心を失ったカノンの身体は、その場につんのめり、勢いよく地面の上に叩きつけられた。手と膝を地につき、跪いたカノンから見上げるミロの面差しは、街灯の影となってよく見えない。
「お前が何をしたのかは知らん。罪を犯したならば償え」
見るというより射るといった方が近い、強い光を放つ眼差しだけが、真っ直ぐにカノンを捉えていた。
「だが、赦されぬ罪などない」
頭上から降り注ぐのは、戒めの太陽か恵みの雨か。青年の声は、思い切り拳を振るった後とは思えぬ静けさで、その奇妙な威圧感に、カノンはやはり圧倒されていると認めざるを得なかった。こんな扱いを受けたのは初めてで、いつものカノンならば、悪態の一つもついてやらねば気が済まないところだ。だが、今は不思議とそんな気にならない。カノンの思考を断ち切るように、ミロは続けた。
「これで良いな。お前たちも」
事の成り行きに圧倒され、場はしんと静まり返っていた。この中で最も年若いミロが主導権を持ち、年長の男らを見渡して鷹揚に言う様は、見ようによっては滑稽である。だが誰一人として笑い声をあげる者はいなかった。
「お前も」
全員を見渡した最後に、ミロは、肩越しのわずかな視線を、カノンに投げて寄越す。
たとえほんの一瞬でも、煌々と輝く青い眼差しは、街灯の明かりなどより、もっとずっと強い光でカノンを照らす。左手に光るバングルには、青く色を変えた文字だけが残った。俺のスティグマ。
つい、数瞬前までのカノンは、世の中の総てを憎んでいた。胸の奥に狂暴な、ずっと昔から飼い続けている猛獣が、爪を研ぎ、背を低くして、牙を剥いて襲かかろうとしていた。どいつもこいつも馬鹿ばっかりだ。何もかもぶち壊してしまいたい。自分の思い通りにならない身体も事態も何もかも。そう思っていた。だが、今は。
渦巻いた濁流がすべて消え失せ、カノンの心中は、静かな碧い水面を湛えていた。制御できない激しい感情の波を、押さえつけるでも、受け流すのでもなく、だが、ミロは確かに流れを変えて見せたのだ。カノンにもわからない、謎めいた何かによって。
「な……それの何がけじめだというんだ」
「待て。契約したのは事実のようだ」
我に返り、まくし立てようとする黒服を制止し、見ろ、と仲間の一人が顎をしゃくる。カノンの左手首のバングルが淡い光を発しているのを確認すると、それまで肩を怒らせていた黒服も肩を落とした。
「かくなる上は、彼も一緒に」
「撤収だ」
それまで無言だったリーダー格の男が、諦めきれない一同を制した。見ると、トランシーバーのような無線機からくぐもった音声が何事かを告げ、インカムで短く返事をする姿があった。黒服たちは、皆一様に姿勢を正し、拳銃を懐にしまいこむ。油断なく彼らの動向を見守るミロの視線に気づいた一人が、ふと思い出したように言った。
「君は同じと言ったが――人間とアンドロイドは違う。それを、よく覚えておくことだ」
しまい掛けた拳銃をさっと中空に向ける。身構えたミロの予想に反して、引かれた引き金から音が発することはなく、青白い電撃が空に走っただけだった。
「スタンガン、か……?」
「人間に当たれば大怪我どころではすまなかったがね」
改めて胸のうちにそれを収め、黒服たちは背を向けて去っていく。
「我々の任務はここまでだ。人間と契約を交わしたアンドロイドを、契約主の意に反して回収することはできない」
原則としてな、と付け加え、最後の黒服が踵を返した。
辺りには静寂が戻り、二つの影だけが再び夜に取り残された。詰めていた息を、ミロがふっと吐き出したのがカノンにも伝わる。カノンもつられて声を漏らした。
「お前……」
「ミロだ」
カノンの方を見たかと思えば、即座に訂正が入る。
「……ミロ」
渋々名を呼べば、ミロは満足そうに頷いた。
「まだ、名前を聞いていなかったな。お前、名は何と言う」
「名前、だと?」
「あるだろう、名前だ」
怪訝そうに首をかしげるミロに、カノンは思ったままを口にする。
「何故」
噛みあわない会話の責任は、今はもしかしたらカノンの方にあるかもしれない。わざとではない。カノンには、ミロの言っていることが咄嗟には理解できなかったのだ。人間ではない。罪を犯したアンドロイド。謎の黒服の男たち。ミロが訊ねなければならないことは、山ほどあるはずだった。今の状況だってそうだ。たまたま奴らがルールに則り撤収したからよかったものの、もしも、カノンもろとも撃たれていたらどうするつもりだったのか。他にもっと言いたいことはあるだろうに、なぜ第一に名前など訊ねるのか。
「何故? 呼べないと困るだろう」
ミロはさも不思議そうに答えた。
「困る?」
今まで名を訊ねられたことなどなかった。それで困ったこともなかった。それが当たり前のことだと思ってきた。『ジェミニのスペア』それがカノンを指す記号。
なのに、この男は、ミロは、カノンに名前を聞くのだ。この俺に。
「……………………カノン」
長い沈黙の理由をミロは知らない。ミロは仰々しく頷き、そして呼んだ。
「カノン、行くぞ」
カノン、と。
あんなことがあった後なのに? 俺は人間ではないのに? 様々な疑問がカノンの頭を巡るが、口にするのは躊躇われた。できなかったと言った方が正しい。思わず頷いた自分に、カノン自身が最も驚いていた。俺には、人に従うプログラムは組み込まれていなかったはずだ。なのに何故――。
カノンの返事を待たず、ミロは、背を向けて颯爽と歩き出す。ついてくるのが当然とばかり、揺るぎない自信と矜持を体現するかのように、色の濃い豊かな金髪が目の前で揺れる。それはカノンにとって得られぬ羨望でもあり、故に憎悪でもあるはずだった。
カノンは出会った相手の顔を忘れない。望むと望まざるとに関わらず、思い出したい時、すぐに取り出せる記憶の箱にしまってあるのだ。どいつもこいつも、たいして特徴もない、似たようなのっぺり顔で、同じような表情しか見せない能面ばかり。そんな奴らの顔など、今すぐ消去してどぶにでも捨ててしまえればどんなにいいか。
今カノンは、目の前で黄金の髪を揺らす青年の顔が見えないことを惜しいと思う。つい先ほどまで凝視していたはずの、ミロの顔。一度記憶したら忘れないはずだ。それで十分のはずなのに、もう一度よく見て、彼の顔を確かめたい。
「おい、カノン。早くしないと置いていくぞ」
ミロが振り返ると、カノンの願いはあっけなく叶えられた。力強い意志を宿す眼光は、カノンをひたと見据え、その姿をありありと映し出す。こいつの顔は能面じゃない。他とは違う、生きている顔だとカノンの直感が悟る。
ミロについて歩き出したその訳を、カノンはまだ、掴みかねている。
*
「ご指示の通り引かせました。ですが、これで宜しかったのですか?」
静かに無線機をおろし、長髪の青年が傍らの少女に問う。後ろで緩く束ねた髪の房が、夜風に揺れた。
「あのままでは怪我人が出ていましたもの。それに、あのようなやり方を、私は望んではおりません」
幼さの残る声色と、少女が身にまとうドレッシーな白のワンピースは、恐らくこの場にそぐわない。だが、ひと回り近く歳の離れているであろう青年に、堂々たる物言いで語りかける姿は、神々しい威厳すら感じさせる。
ともすれば女性的とも取れる面差しに憂いの色を滲ませ、青年は首を振った。
「彼らは優秀なエージェントです。しかし、アンドロイドは時に危険な存在。特に彼は――」
「わかっています。でも、彼が素直に人間の言うことを聞いたのは、これが初めてです。見過ごせない変化が起きているように、私には思えます」
どこか楽しげに言って、少女は口元をほころばせる。
「彼は確かに異端です。他のどのアンドロイドとも違う。でもそれは裏を返せば、他のアンドロイドとは一線を画する、特別なアンドロイドになり得る可能性を秘めている。そんなふうに感じるのです」
風を受け、路傍の草木が小さくさざめいた。閑静な町に突如として訪れた異変を察知して、不安がるようでもある。
「彼が――カノンが、かつて犯した過ちを悔いて生まれ変われるのならば、過去のことは全て免罪し、廃棄処分の件は白紙に戻したいと思います。いかがでしょう」
ぴん、と一本の細い糸が張り巡らされたような緊張が走った。少女はまるで是非を問うような言い方をする。だが青年にとって、少女の言葉は特別な意味を持っている。彼女が是と口にすれば、それがどんな道理であろうと、通さぬわけにはいかないのだ。
「貴女の決定は我が社の総意ですよ、アテナ」
「沙織と呼んで下さい」
青年の心中を知ってか知らずか、少女は笑みを絶やさず、穏やかに言葉を継いだ。
「私は、あなた個人の意見を聞いているのです、ムウ」
ムウと呼ばれた青年は、困ったように一つ息をついた。
「スペアとして扱われていたもう一人のジェミニ。彼は欠陥品です。アンドロイドとしてもっとも大切なプログラムが欠けている。今となっては修正もかなわない。私は、貴女のような希望的観測は持てません」
「あなたのそういうところを、私はとても高く評価しています」
満足げにうなずいて、沙織は遠く夜空を見上げた。月は出ていなくとも、瞬く星のさやけさが、少女の白い頬を映して輝いている。
「あの青年、ミロと言いましたか。彼はあなたと同じ敷地内の住人でしたね」
「その通りです」
「では、サンクチュアリ社の最高経営責任者として、あなたに命じます。二人の監視を。少しでも変化が現れたら、逐一報告してください。万一、カノンが人間に危害を加えるようなことがあれば」
そこで言葉を途切れさせた沙織は、この時はじめて表情を曇らせた。だが、すぐににこやかな口調に戻って言った。
「そのようなことのないよう祈ります」
そして再び花のような笑顔を咲かせる。
夜の町を仄青く照らす街灯と空の星々の光が、春の宵に起きた喧騒の締めくくりを、静かに見守っていた。
夜の闇に咲く輪の花。蕾を開く音が、どこかでもう一度鳴り響いた、気がした。