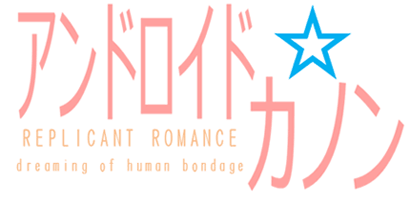
第一話 そのアンドロイド、不良につき②
高い石壁と家の外壁に囲まれた通路に人影はない。酷使した心臓が血液を送り出す音と、アスファルトを打ち鳴らす足音だけがうるさいくらい耳に響く。視界の端に映り込んだ今にも消え入りそうな古い街灯が、チカチカと不規則な点滅を繰り返すのが不気味だった。切迫した呼吸をととのえることも許されず、息苦しさに喘ぎながら、ミロは憤っていた。
「――おい!」
何度目かになる抗議の声が夜の静寂をつんざいても、男はまったく意に介さず、迷路のような通路を駆けた。男への怒りに任せ、アスファルトを思い切り踏みつけながら走っていたせいで、向こう脛のあたりが引き攣るような痛みを訴えている。走る勢いのそがれる岐路にさしかかるたび、ミロは何とかして男の手を振りほどこうと躍起になるのだが、残念ながら徒労に終わった。
ミロとて腕っぷしにはそれなりの自信がある。なのにこの男ときたら、さっきまで行き倒れかけていたのが嘘みたいな馬鹿力で、ミロの手首を強く捕らえたまま、抵抗に遭ってもびくともしないのだ。
走りながら、男は一度もミロの顔をかえりみなかった。ただ時折、ミロがそこにいることを確かめるように、何度も指先の力を込め直す。痛いほど強く食い込む爪先からは、絶対に逃してなるものかという意地のようなものが感じられ、ぴたりと這わされた指先の腹からは、縋るような必死さが伝わってくる。こんなふうに誰かに強く手を引かれたのは初めてで、なぜ俺がという怒りを覚えつつも、いつしか抵抗をやめたミロは、黙って男に並走することにした。
どれくらい走り続けていたのか、たどり着いた先は、悲劇的なことに袋小路だった。ここまでよどみなく走ってきた男も、さすがに衝撃を受けたと見え、来た道を戻るのかと思いきや、黙ってその場に立ち尽くしてしまった。
ミロは男の横顔と、繋がれた手とを見比べた。街灯の仄青い明かりに照らされた頬は色を失ったように白く、美しいと感じた造作は、ひどくやつれていっそ哀れみを誘うようにも見える。
依然として男の手に込められた力は強い。だが、ほんの一瞬、男が諦念に囚われた気配を、ミロは確かに感じ取った。渾身の力を込め、ミロは男の手を思い切り振り払った。
「貴様」
男は弾かれたように顔を上げ、そこで初めてミロの顔を正面から見た。ミロよりも、若干目線が高い。
「ミロだ。どういうことか説明しろ」
「……ご丁寧に自己紹介をどうも」
ようやく合った視線を男はすぐにはずし、うつむいてからぼそりとアスファルトに言葉を落とした。
「人を巻き込んでおいて茶化すのはよせ。追われているのはお前だろう」
男は黙っていた。沈黙は拒絶であり、防御でもある。例の黒服たちが追っているのがこの男であるのは明らかだった。追われて逃げるような男が、そう簡単に真実を話すわけもない。目を合わせないのにも、何かやましいことがあるのに違いなかった。だが、ミロはこのまま男を捨て置く気にはなれなかった。
「一体何をした。なぜあのように物騒な連中に追われている」
若者らしい気短な質と、若さゆえの好奇心と。だがそれ以上に、ミロは知りたかった。一瞬だけ交錯した、海を思わせる瞳の碧。ミロの腕を捕らえた指先に込められた、強い何か。波間に煌めいては消える光を追うように、見過ごしてはいけないと、ミロの内の何かが訴えかけていたからだ。
自由の身になれたというのに、逃げることも忘れ、ミロは鋭い眼差しで男をぴたりと見据えていた。
「知ってどうする。貴様には関係のないことだ」
「関係ないわけあるか。だったら俺は最初からここにいない」
「取り返しのつかない悪事だと言ったら?」
ミロの瞳が剣呑な光を帯びて輝いた。
「命を狙われるほどのか」
「さあな。実は俺にもよくわからないんだ」
これは嘘だ。ミロの直感が囁いた。男は軽く口の端を上げ、わざと煽るような台詞を選ぶ。だが、そんな舌戦に乗ってやる必要はない。
「なぜ俺を連れてきた」
かまわず問い詰めるミロに、男は道化のような仕草で、わざとらしく肩をすくめた。
「連中、お前には手が出せないんだ。そういうルールでな。だから利用させてもらった」
どこまでが真実で、どこからが嘘か。嘘の中にひとつまみ混じった真実はどれか。ミロの眼光は、それを見極めようと、男の瞳を離さなかった。
「わけを話せ。事と次第によっては、聞いてやらんこともない」
ミロは首を静かに振った。男の瞳孔がすっと大きくなる。
「お前」
「お前じゃない、ミロ、だ」
ミロ。男は唇の動きだけで、その名を反芻した。ミロ。
今宵二度目の静寂が破られた。バタバタと慌ただしい足音が二人を囲む。ミロは背後を振り返った。
「見つけたぞ、ジェミニのスペア」
いつの間に追いつかれていたのか。拳銃を据え、二人の退路を断つように立ち塞がったのは、黒服の男たちだ。舌打ちが聞こえ、乱暴に肩を掴まれたかと思うと、ミロの体は黒服たちの方へ突き出された。もんどり打って倒れそうになるところを、左肩から腕にかけて後ろ手に捻り上げるようにして支えられ、ミロは思わず呻き声を上げた。これではまるで急しつらえの弾よけだ。憤然としたが、息を吐き出して痛みを紛らわすことしかできない。
禍々しい四つの銃口は、ミロを前にしてやや怯んだように見えた。男に向けられた敵意が収まることはなかったが、黒服たちは戸惑うように、互いに目配せし合っている。
ミロを盾に据えたまま、男はじりじりと後退した。これ以上、後はない。耳元で、男の低い声がした。
「聞いてやると言ったな」
今までの調子とは明らかに異なる、切羽づまった声音だった。ミロの返事を待たずに、男は続けた。
「俺と契約しろ」
声こそ上げなかったものの、ミロは痛みに耐えるように歯を食いしばった。男の力が一際強まったからだ。顔を反らし、ミロは掴まれた肩にかかった男の左手に目をやった。Blood Pact――そこでミロは、初めて、男の左手首に巻きつくバングルに、文字が浮かび上がったことに気づいた。
バングルを食い入るように見つめるミロに、どうやら男の方も気づいたようだ。
「安心しろ、必要なのは血じゃない。指紋だ」
「何を、言っている」
「いいから言う通りにしろ。すぐに終わる」
「ふざけるな! このっ……!」
長い指先に噛みついてやろうか。ミロの頭についぞ血が上った時だった。
「何をぶつぶつと話している」
黒服の一人が声を荒げた。彼らを無視したミロたちのやり取りに、苛立ちを隠せない様子だ。
「ジェミニのスペア。お前、自分のしたことが分かっているのか」
「無論。俺は正常だ。そっちこそ、随分と早いご到着だ。サンクチュアリ社はさぞかし優秀な測位システムを採用しているのだろうな」
「黙れ。何もかもお前のせいだろう」
「何のことだか」
ミロは背後にいる男の表情を見返り、仰ぎ見た。状況は、誰がどうみても絶体絶命、四面楚歌。だというのに、渦中の男は、あろうことか不遜とも取れる笑みを浮かべている。
「お前の身柄は発見次第、拘束しろとの命令が出ている。手段は選ばず、ともな」
感情を抑えた声で、もう一人が口を開いた。すぐにかぶせて嘲る調子が続く。
「ふん、廃棄処分は既に決定しているようなものだ。罪を犯したお前には似合いの処遇だ」
「罪? お前たちの決めたルールなど、俺の知ったことか。気に入らなければ即廃棄。そうすればなかったことにできると思っている。低能な人間のやりそうなことだ」
「なにを……!」
ミロは目を瞠った。人を食ったような言い回しと澱みない弁舌は、起死回生の一手があるかのように錯覚させる。それがこの男の言う契約とやらと、何か関係があるのか。何より男は、その場に立っていることすらままならぬほど疲弊しきっているはずなのに、この貪欲ともいえる生命力は、いったいどこから来ているのか――。
「貴様らに俺を裁ける権利などあると思うな!」
ミロの思考を遮るように、男が鋭く言い放つ。気色ばむ黒服らの気迫に押され、一歩下がるように見せかけて、男はミロにだけ聞こえる低い声で言った。
「もう一度言う。俺と契約しろ。悪いようにはせん」
すでに十分悪いように扱われているのだが、口答えする余裕はミロにもなかった。かといって、意味も分からぬまま、この男の思い通りになってやるつもりもない。ミロの手強い抵抗に、男が苛立たしげに歯ぎしりしたその時、後ろに控える黒服の一人が、舌打ちと共に小さな声で吐き捨てるように零した。
「欠陥品のくせに」
――刹那、空気が変わった。
文字通り、男の纏っている空気が、瞬間にして青白く燃え上がったのを、ミロは見た。比喩ではなく、見えたと思う。銃口を向けられても慌てるそぶりを見せず、罪人だと言われても眉一つ動かさなかった男が。
「欠陥品だと……!? この俺をッ!」
制御できない感情がほとばしる瞬間。痛みでも苦しみでもない、何かもっと別の強い感情。
「貴様らこそ、飼い主の言いなりにしか動けぬ能無しの分際で!」
こんなふうに激しい一面を、いとも簡単に晒すような男には見えなかったのだ。少なくとも、つい今し方までは。
ミロを掴んでいた左手は、いつの間にか離れていた。美しいと感じた碧眼は、ほとばしる怒りに今はらんらんと輝き、凪だったのが嘘みたいに、今は荒れ狂う嵐の海の様相を呈していた。誰一人として、その激しくうねる海面に触れることはできない。触れたが最後、囚われて、息をつく間もなく呑み込まれるだけだ。
「俺は違う。誰の言いなりにもなるものか。俺は俺だけのために、好きなように生きる。邪魔する奴は全て排除する」
男に巣くう激しい感情の高波が、真っ白な飛沫となって硬い岩肌を打つ。しかし、その荒々しさにいっとき圧倒されても、最後に砕かれて霧散するのはいつだって海の方だ。
「それの何が悪い!!」
一瞬だけ、痛みに耐えるように目を伏せた男の表情を、ミロは見逃さなかった。宣言するというよりも、まるで自分に言い聞かせるような。
はじめは怒りに身を任せるばかりかと思った。だが違った。男は、自分自身が生み出す荒々しい波頭に今にも呑み込まれそうになっている。そして溺れるまいと必死に足掻いているのだ。
「生きる、だと? 馬鹿な。その思考こそ、お前が欠陥品である動かざる証拠だ」
黒服たちが口々にする非難の声は、もはや男を追い詰めるだけだ。そんなこともわからないのか。ミロは歯がゆさに唇を噛みしめた。男の瞳を輝かせるのは、ほとばしる怒り、そしてやるせなさ。そうだ。先ほど、掴みそうで掴みかねていたものは、きっとこの内なる光だったのだ。
「上の沙汰を待つまでもない。この場で処分してくれる――」
「そこまでだ!!」