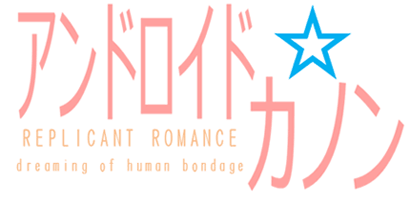
物心なんてものが備えつけられていたのか、甚だ疑問だ。けれどカノンは、カノンを取り巻く世界の事情について、なんとなく理解するようになった頃から、左の手首に纏わるバングルが大嫌いになった。
カノンを監視するみたいに、いつも、どこまでもついてくる月や太陽ですら、雲に覆われれば姿を隠すのに、このバングルときたら、どこへ行くにも何をするにも、常にカノンと一緒なのだ。
あまりにも煩わしくて、いっそ腕ごと引き千切ってやろうとしたこともある。だが想像したよりおおごとになってしまい、結局諦めた。バングルには特殊な仕掛けが施してあるらしく、無理に身体から離そうとすると己の身が危ういということを、カノンはその時初めて知った。
つまりどうあっても、カノンには、バングルと共に在る以外の選択肢はないらしい。
執念深く諦めも悪いカノンだが、損得を推し量るのは得意であったから、バングルを外そうとあれこれ策を講じるのが、時間の浪費だと悟るのも早かった。
それから後、カノンは、憎悪と呼べるくらいたぎらせていたバングルへの執着を、すっかり失ってしまったかに見えた。どころか、手首をくるくると返して色んな角度から眺めてみたり、天にかざしてみたりと、まるでお気に入りのアクセサリみたいに扱ったものだ。
カノンがバングルをいじるたび、左腕が取れかけた時、死に物狂いで阻止しようとした連中の顔が緊張に引き攣るのが、カノンには滑稽でたまらなかった。困惑と憐憫、忌避、それから罪悪感の入り混じった彼らの表情を見たくて、カノンはわざと人目のあるところで、左手とともにバングルを空へ差し出した。
おかしな奴らだ。俺を可哀想だと思うのなら、今すぐこの厭わしいスティグマを取り払ってくれたらいいのに。
古代ギリシャでは、奴隷や罪人など、社会的に差別された人間に押された烙印のことをスティグマと呼ぶ。俺たちにぴったりじゃないかと、どこかの書物でそれを知ってから、カノンは我ながらその考えを、いたく気に入ってしまったのである。
ともかく、以来カノンは二度と自分でバングルを外そうと試みたことはなかったし、連中への当て擦り以外で、外したいと思ったことは一度もなかった。
*
皮膚がじりじりと焼き焦げる感覚と、それに伴う独特の異臭はひどく不快だ。これでは本当の焼きごてになってしまうと、カノンは懐かしい昔話を思い出し、一人笑った。
今、カノンの左手首に巻きつくバングルは、これまでにないほど異常な熱を帯び、不気味な鈍色に輝いている。増加し続ける熱量は膨大、危険信号だと考えるまでもなく理解していた。
どうせなら、手首ごと焼き切ってくれたらいいものを。
昔のカノンならば真っ先に望んだだろう。だが、今は困る。
あの時左腕を失わずにすんで良かった。止めてくれた連中に心から感謝しようとカノンは思う。
返した手首の付け根付近にある窪みに触れてから、指の腹でバングルの側面をさすり、内甲を辿る。バングルは燃えるように熱く、触れただけで指の皮膚が音をたてて爛れたが、構わなかった。
バングルの内側に刻まれたアルファベットの刻印をもう一度確かめると、カノンは、碧い双眸を静かに閉ざした。
Android Kanon
REPLICANT ROMANCE
dreaming of human bondage
カノンを監視するみたいに、いつも、どこまでもついてくる月や太陽ですら、雲に覆われれば姿を隠すのに、このバングルときたら、どこへ行くにも何をするにも、常にカノンと一緒なのだ。
あまりにも煩わしくて、いっそ腕ごと引き千切ってやろうとしたこともある。だが想像したよりおおごとになってしまい、結局諦めた。バングルには特殊な仕掛けが施してあるらしく、無理に身体から離そうとすると己の身が危ういということを、カノンはその時初めて知った。
つまりどうあっても、カノンには、バングルと共に在る以外の選択肢はないらしい。
執念深く諦めも悪いカノンだが、損得を推し量るのは得意であったから、バングルを外そうとあれこれ策を講じるのが、時間の浪費だと悟るのも早かった。
それから後、カノンは、憎悪と呼べるくらいたぎらせていたバングルへの執着を、すっかり失ってしまったかに見えた。どころか、手首をくるくると返して色んな角度から眺めてみたり、天にかざしてみたりと、まるでお気に入りのアクセサリみたいに扱ったものだ。
カノンがバングルをいじるたび、左腕が取れかけた時、死に物狂いで阻止しようとした連中の顔が緊張に引き攣るのが、カノンには滑稽でたまらなかった。困惑と憐憫、忌避、それから罪悪感の入り混じった彼らの表情を見たくて、カノンはわざと人目のあるところで、左手とともにバングルを空へ差し出した。
おかしな奴らだ。俺を可哀想だと思うのなら、今すぐこの厭わしいスティグマを取り払ってくれたらいいのに。
古代ギリシャでは、奴隷や罪人など、社会的に差別された人間に押された烙印のことをスティグマと呼ぶ。俺たちにぴったりじゃないかと、どこかの書物でそれを知ってから、カノンは我ながらその考えを、いたく気に入ってしまったのである。
ともかく、以来カノンは二度と自分でバングルを外そうと試みたことはなかったし、連中への当て擦り以外で、外したいと思ったことは一度もなかった。
*
皮膚がじりじりと焼き焦げる感覚と、それに伴う独特の異臭はひどく不快だ。これでは本当の焼きごてになってしまうと、カノンは懐かしい昔話を思い出し、一人笑った。
今、カノンの左手首に巻きつくバングルは、これまでにないほど異常な熱を帯び、不気味な鈍色に輝いている。増加し続ける熱量は膨大、危険信号だと考えるまでもなく理解していた。
どうせなら、手首ごと焼き切ってくれたらいいものを。
昔のカノンならば真っ先に望んだだろう。だが、今は困る。
あの時左腕を失わずにすんで良かった。止めてくれた連中に心から感謝しようとカノンは思う。
返した手首の付け根付近にある窪みに触れてから、指の腹でバングルの側面をさすり、内甲を辿る。バングルは燃えるように熱く、触れただけで指の皮膚が音をたてて爛れたが、構わなかった。
バングルの内側に刻まれたアルファベットの刻印をもう一度確かめると、カノンは、碧い双眸を静かに閉ざした。
REPLICANT ROMANCE
dreaming of human bondage
第一話 そのアンドロイド、不良につき①
敷石で舗装され、ライトアップされた街路樹が整然と立ち並ぶメインストリートから一本裏手に入ると、狭くて雑多な裏路地に出会う。石造りの古い家屋がひしめき合う窮屈な通りは、建物と建物の間が道幅の狭い通路になっており、さらにそこへいくつもの細い路地が交差して、複雑に入り組んだ迷路のようだ。立ち入れば二度と同じ場所へは戻れないかもしれない。一見してそんな不安を抱かせる。月明かりのない夜は暗く、一歩先の足元さえおぼろげで、頼りない。
どいつもこいつも馬鹿ばっかりだ――高台へと続く、暗くて狭い石段を一歩一歩踏みしめながら、カノンは呪っていた。激しく内に渦巻く昏い情念だけが、今にもくずおれそうな身体を突き動かしている。
湿っぽい潮の香りと騒がしい波音から解放されて、どれくらいの時が経ったのか、今のカノンには知るべくもない。ただ一つ言えるのは、行き場を失ってとぐろを巻く、強い憤りをぶつける場所を探している。目覚めてから、ずっと。
先刻から、カノンはひどい目眩に襲われていた。頭の芯がじんわりと熱を放ち、手足に力を込めようとするたび、全身が軋むような悲鳴をあげる。気怠さは収まったものの、時おり靄がかかったようにかすむ視界が煩わしくてたまらなかった。主の言うことを聞けない身体なら、いっそ四肢をバラバラに裁断して、総取り替えしてやった方が早い。
思うように働かない身体を引き摺って、長い石段をようやく登り切ったところで、カノンは足を止め、眼下に広がる夜の町を見下ろした。
緩やかなカーブに沿って湾岸通りを導く街灯や、夜道を流れる赤血球みたいなテールランプ、市街地に煌々と輝く自己主張の強いネオン、家々に灯る優しい光、その一つ一つを残さず掻き集めて、粉々に打ち砕いてやりたい。まるで子どもの癇癪だが、誇張でも比喩でもなく、自分にはそれができるという感覚がカノンにはあった。
夜空に一閃、大輪の花が咲いた。
赤、青、黄、緑、橙。闇色のカーテンにちりばめられた極彩色のスパンコール。きらきらと中空に舞う光の残滓は、夜の雲居を照らし、やがて夜空に紛れ消えてゆく。
カノンは咄嗟に背後を振り返った。辺りが閃光に照らされるのと同時、誰かの視線を感じたような気がしたからだ。
ただの打ち上げ花火か。
発火地点とおぼしき場所に、七色にライトアップされた大きな輪っかが見える。そこには、巨大な観覧車がゆったりと体を回していた。中心から円周に向かって伸びる幾筋もの光線が、幾何学模様のパターンを描いて、規則正しく無限に繰り返される様は、万華鏡のようでもある。
辺りに異常がないことを確かめると、色あせて白っぽくなった石段を蹴って、カノンは素早く踵を返した。緩やかな登り坂が終わったと思えば、今度は急な下り坂になる。勢いに煽られながら、カノンはできるだけ身を低くして、夜道をひたすらに駆け抜けた。
*
桜の木も見頃が終わり、葉桜になってから暫く経つ。日差しは柔らかく、若葉の新緑が眩しい季節になっていた。とはいえ、宵の口はまだ冷える。春の夜気が孕む風の冷たさを肌身に感じ、ミロはぶるりと大きく肩を震わせた。
希臘町は、海と丘陵地帯に囲まれた土地を開拓してできたベッドタウンである。町の最北端・星ヶ丘を頂点に、閑静な住宅街として人気を博すここ南西部から、もっとも近代化の進む中心部を通過して、海に面した南部旧市街までを繋ぐ三角形状に幹線道路が敷かれている。結果、どこへ向かうにも避けて通れない坂道と吹き上げる海風が、この町を特徴づけることとなった。
強い追い風に、長い髪が煽られて舞う。足早に家路への坂道を上るミロは、煩わしそうに片手で髪を払ってから、手元に目を落とした。手にはファスナーの一部がほつれた小さな財布が握られている。もう一度財布の中身を確認し、ミロは深々とため息をついた。
四万とんで五百円。なけなしの貯金は別にして、これが、現在ミロが自由にできる全財産だった。先月は、春休みのおかげでいつもよりバイトに精が出た。その甲斐あって、懐具合はまずまずといったところだが、翌月には大学の教材費という名目で、月収の半分ほどがあっという間に飛んでいってしまう。春は何かと物入りの季節なのだ。
給与が出たばかりだというのに、すでに来月分の収入と支出に頭を悩ませながら、ミロは暗い路地へと足を踏み入れた。
都市開発は進んでいるものの、希臘町では景観の保護を理由に、一部地区では街灯の数や明度が制限されている。ミロが選んだ裏路地もその一つだ。日が暮れると同時に、あっというまに閑散となる。だが、車量も通行人も多いメインストリートに比べると格段に歩きやすいため、ほんの五分程度だがショートカットになるこの路を、ミロは普段から好んで使っていた。
人影のない、慣れた夜道を足早に歩く。今後いかにして生活費を工面するかについて、ミロは何度目かの結論を導き出そうとしていた。
家賃は格安の物件だし、大学とバイトの往復で、そもそも家にいる時間がほとんどない。水道光熱費も必要最低限にとどまっているはず、ということは、削られるべきはやはり食費か。
まばらな街灯に群がる羽虫を尻目に、眉間に皺を寄せながらいつもの十字路に差しかかったところで、ミロは、ふと先を行く不審な影に目を留めた。
影はおぼつかない足取りで、怪我でもしているのか、それとも気分が悪いのか、膝に手をつき、苦しそうに肩で息をしている。少し癖のある長い髪が、腰の辺りでさらさらと揺れた。
時刻は午前零時を回ろうという頃合いだ。さては酔っ払いかもしれぬと眉をひそめるが、かといって、目に留めてしまった以上放っておく訳にもいかず、ミロは仕方なく眼前の人影に声をかけた。
「おい」
男の身体が、傍目にもそうと知れるほど強張ったのがわかった。さては関わってはいけない類いの人種だったかと、ミロが判断するよりもはやく、男は身を翻し、ミロとの間の距離を一気に詰めた。しなる両腕が恐ろしい速さで伸び、ミロの頭を左右から掴もうと迫る。側頭部に触れた指先に力が込められるまで、あまりにも一瞬の出来事で、ミロは声すら発せなかった。
やられる――身構えたミロの思考に反して、いつまで待ってもその時は訪れなかった。
男の身体がぐらりと傾ぎ、次の瞬間、アスファルトに片膝をつく。ミロは反射的にその背を支え、ぎょっとして男の顔を覗き込んだ。男の肩から腕にかけてはハッとするほど冷たいのに、背中だけが異様に熱い。身体中の熱が集まっているのではないかと錯覚するほどに。
「……追っ手じゃないのか」
ぜいぜいと荒い息の下で、男は言った。
「何?」
低い声音は聞き取りづらく、ミロは耳をそばだてた。だが男の口からそれ以上の言葉が発せられることはなかった。話す気がないのか、いや、実際に口を動かすことすらままならぬ状態かもしれない。うずくまって双肩を揺らす様は、限界を振り切って今にも倒れそうなアスリートのようだ。
このまま道端に転がしておくわけにはいかない。違和感を頭の隅へと追いやり、ミロは男の身体を路傍まで引き摺って行った。壁に背を預けると、男は長い手足をだらりと投げ出し、浅い呼吸を何度も繰り返した。
しばし考え込むと、ミロは思い出したようにメッセンジャーバッグから飲みかけのペットボトルを取り出した。ペットボトルには、半分ほどだがミネラルウォーターが入っている。何も口にしないよりはましだろうと思ったのだ。
男の目線と合うよう膝をつき、ミロはそこで初めて相手の顔をまじまじと見た。疲弊しきっていても整った眉目は、ちょっとやそっとではお目にかかれないほど秀麗で、ミロは一瞬目を奪われた。長いまつげに縁取られ、うっすらと持ち上げられた瞼から覗く瞳は、晴れた日の紺碧の海を思い起こさせる。こんな時なのに美しいと感じた。
差し出されたペットボトルを力なく受け取った男は、しかしそれに口をつけようとはしなかった。密封された空間の中で、たゆたう透明な水をぼんやりと見つめ、それから胸に抱え込むようにして、自らの心臓のあたりに押しつける。覗き込むと、男の眉間から縦皺が消えていることに、ミロは気がついた。
ペットボトルを抱いたまま、男が動かなくなってしまったので、ミロは彼の隣にそっと腰を下ろした。背にした壁はひんやりとして、火照った身体の熱を奪うだろう。黙って見つめているだけというのも気が引けて、何となく顔を上げると、路地裏を囲む白い石壁の先に、四角く切り取られた夜空が浮かんで見える。そうだ、暗いと思ったら、今夜は月が出ていなかったのだ。
夜の静粛が、不調法にも破られる。突如として、狭い路地裏に複数の足音が響いた。
ミロはハッとして辺りを見渡し、思わず絶句した。どう見ても堅気には見えない黒服の男が、前方に一人。後方に三人。まるでミロたちの行く手を遮るように、周囲を取り囲んでいた。全員かなりの上背があり、それだけでも威圧的だが、さらに驚いたことには、片手に拳銃のようなものを携えている。鈍く光る銃身。彼らが何か――何か危険なものを追っているのだと、ミロは本能的に悟った。だが、ミロにはそのような心当たりがない。
じり、と靴底が地面をこする音がして、前方にいたリーダー格と思しき黒服が、距離を詰めようとにじり寄るのがわかった。反射的に退こうとしたミロの右腕が、強い力に奪われる。隣にだらしなく背を預けていた男が、一瞬で身を起こし、ミロの手を取ったのだと理解するまで数瞬を要した。
慌てて拳銃を構える黒服らの姿。照準を絞る。だが、引き金が引かれることはなかった。
ペットボトルが中空を舞い、中身が黒服にぶちまけられる。ただの水だが、それでも十分効果はあった。
驚いた黒服が戸惑う隙をついて、ミロは、男とともに狭い路地の間を駆け抜けていた。