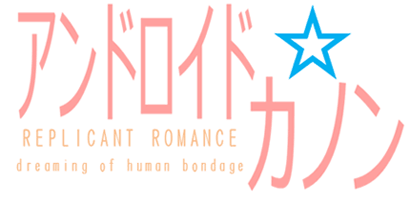
第弐話 KANON STRIKES!⑤
「いいか、卵は駅前のスーパーで十個入り一パック九十八円が底値だ! この時以外に買うことは禁止する! 牛乳は成分無調整一リットル百三十八円で火曜日が特売だと覚えておけ!」
「非効率的だ。なぜいちいち別の店で、別の日に買い物をせねばならんのだ」
「少しの手間で安くて美味いものが手に入るのに、なんだその言い草は。それに、商店街を利用することで地域の活性化に繋がるだろう」
「そんなもの俺の知ったことか!」
「アンドロイドというのは買い物もまともにできんのか!? 何のための高性能だ」
沈みかけた夕陽が石畳に二人分の影を長く映し出す頃、カノンとミロはめぞんゴールドの共同玄関に到着した。道中ずっとこの調子で歩き続けているため、近所迷惑この上ない。
二人まくしたてながら共同廊下を渡り、ミロの部屋の手前付近を通りかかったあたりで、隣室の住人が顔を出した。額のビンディと腰まである黄金のストレートヘア、女性的な民族衣装を着こなしているのが特徴的だ。しかし何よりも特筆すべきは、彼が瞳を閉じたまま歩き、会話をすることだった。
「ミロ、アンドロイドを持つことにしたのかね」
カノンの左手のバングルに気づいたらしい。ミロは彼の名をシャカと呼んだ。ちなみにれっきとした男性である。
「成り行きでな。さっそく後悔しているところだ。うるさくて敵わん」
なんだと、とミロに食ってかかろうとするカノンを眺めやり、シャカはふむと顎に手を当てた。
「なかなか難しそうなアンドロイドだ。手に負えなければ、携帯型に固定してしまえばいいのではないか」
往来の手のひらに収まるサイズのものを携帯型というらしい。ミロはサンクチュアリ社でもらったばかりの分厚い冊子の目次を目で追った。だがどこにもそれらしき項目はない。
「載っていないぞ」
「妙だな。契約は済んでいるのだろう」
首を傾げるミロとシャカを一瞥して、カノンはフンと鼻を鳴らした。
「俺を並みのアンドロイドと一緒にするな。俺は自分の意思で自由に姿を変えることが出来る。誰の指図も受けるものか」
しらけた表情を見せるカノンを前にして、ミロははたと気づいたようにアンドロイド取扱説明書から顔を上げた。
「お前、先ほどショップで突然いなくなったのも、その機能を使ったのではあるまいな」
ちらりと視線を寄越しただけで、無言でぷいとそっぽを向くカノンに、ミロは疑いを確信にかえる。
「姿を消して悪事を働くなど、」
「悪事じゃあない。効率の追求だ。それに消えるわけでもない。小さくなるだけで、姿はある。まあ、多少は目立たなくなるがな。気づかぬ方が注意力散漫というやつだ」
「屁理屈をこねるな!」
旗色が悪いと見て取ったか、カノンはふいに身を翻し、もと来た共同玄関へと引き返していった。
「おい、どこへ行く!?」
「野暮用だ」
振り返ることもしないカノンに、ミロは更に言い募ろうと肩を掴む。
「!?」
が、掴んだはずの右手はすかっと空を切り、カノンの姿は忽然と消えていた。本人の言を信ずるならば、消えたわけではなくどこかにいるはずなのだが、薄暗い廊下では見つけることは不可能だった。だいたい、携帯型というのがどういう姿なのか、ミロは知らない。
「まったく」
ミロは大きく溜息をついた。
「勝手なやつだ」
もっとも、出会った時からこの調子なので、今更驚くほどのことはない。
「いいのかね?」
一連のやりとりを目を瞑ったまま見ていたシャカが、ミロに訊ねた。
「GPS機能を使えば、位置確認は可能のはずだが」
「好きにさせておく」
ミロは首を振った。カノンの気まぐれに付き合っている暇はない。これからミロは、失われた貯金と明日からの家計のやりくりについて、対策をたてねばならないのだ。カノンとの共同生活は、始まったばかりなのである。
*
夕陽が沈むと、辺りにはあっという間に夜の気配が漂いはじめる。カノンは、めぞんゴールドの敷地からやや離れた場所にある、人気のない一角で、姿を現した。お互いその方が都合がよい。外野に余計な邪魔をされなくてすむからだ。
カノンの視線の先には、夕闇に溶け込むように、柔和な顔つきの青年がたたずんでいた。
「はじめまして、カノン」
青年は柔らかい雰囲気を崩さぬまま、カノンに話しかけた。
「私の名はムウ。めぞんゴールドの大家をしている者です。挨拶が遅くなり、申し訳ありません。どうかお見知りおきを」
対するカノンは、剣呑な表情を変えようともしない。わざと聞こえるように大きな舌打ちをした。
「フン、しらじらしい。サンクチュアリ社の犬は、とんだ狸というわけか」
「気づいていましたか」
別段驚いた風でもなく、取り繕うでもなく、笑みを絶やさずムウと名乗った青年は、あっさりと答えた。
「ここに来て以来、うっとうしい気配が纏わりついて、いい加減うんざりしていたところだ。そういえば、本社でも感じたな。おおかた、どこぞやからのぞき見でもしていたのだろう。まったく趣味の良いことだ」
すべてお見通しだとでも言いたげに、カノンは口の端をゆがめて笑う。相手を侮蔑するのと同時に、どこか自嘲するような笑みでもあった。
「それに――」
カノンは自らの眉間をとん、と指さして見せた。
「お前の眉には見覚えがあるからな」
人を食ったようなカノンの態度に臆することもなく、ムウの面持ちは変わらなかった。カノンの声音に苛立ちが混じる。
「それが今になって、俺の前に姿を見せるとはどういう風の吹き回しだ? ご主人様の命令で、警告でもしに来たか」
カノンは挑発するように、わざと芝居がかったセリフ回しを選んでいる。表情にこそ出さなかったが、ムウは目の前のアンドロイドを、注意深く観察していた。
「いいえ。私の一存です」
カノンは一瞬、意外だといった顔つきを見せる。
実際に対面してみて、あらためてわかったことがある。アンドロイドは人間に似せて作られている。感情を持たないアンドロイドは、あらかじめ用意されたプログラムから、その場の状況に応じた感情を選択することによって、時に皮肉やジョークを交えた複雑なコミュニケーションを取ることが可能である。そういったプログラムの性質上、どこかしら、反応の遅れや作り物くささがぬぐえないものなのだ。が、カノンにはそれがまったく見当たらなかった。どう見ても人間そのもの、ただ一つ、左腕のバングルを除いては。
「サンクチュアリ社は、今の俺がどういう立場にあるか、とっくに知っているはずだな?」
意図の読めないムウの来訪になかば焦れてきたのか、カノンは話題の先を急いでいるように見えた。カノンが知りたいのは、自らの処遇に違いない。ミロとの契約が成り立った今、おいそれと所有アンドロイドに手出しすることはできない。しかし、確証はないはずだ。
「社の公的な見解を、あなたに伝える義務は、私にはないのですが……」
ムウは内心を悟られぬよう、淡々と言葉を紡いだ。
「挨拶が遅れたお詫びに、特別にお話ししましょう」
話す間もカノンから目を離さず、すっと息を吸い込み一息の元告げる。
「猶予期間を設ける。処遇は一時保留。あなたとあなたの契約主に我々は干渉しない。これが上層部の意向です」
その視線を感じてか否か、カノンの心中は、巧みに繕った表情からは見て取れなかった。
だが、十分な収穫はあった、とムウは判断する。試験データ上ではすでに確認済みだった機能面での優秀さ以上に、高度な判断力、適応力、順応性は、予想を遙かに超えていた。既存のゴールドマークアンドロイドに勝るとも劣らない、いや、それすら凌ぐ卓越した能力をもつアンドロイドであることは、疑いようがなかった。けれども同時に、選択するプログラムの偏り――特に人間に対する不信感と攻撃性、喜怒哀楽のゆらぎ、言い換えると『感情』の不安定さが、この短期間の間にも様々な場面で露呈していた。最高のアンドロイド足り得るポテンシャルを持ちながら、アンドロイドが本来持ち得ないはずの欠陥が共存する矛盾、それがカノンという存在の異質性なのだ。
ムウは、ふいに踵を返した。
「さて、私はこれからめぞんゴールドに帰りますが」
短く切って、ムウは続けた。
「そこまでご一緒しますか?」
「……ふざけているのか」
初めて、本気で嫌な顔を見せたカノンに、ムウはやはり笑顔で返した。
その場から立ち去ろうとして、ムウは足を止める。そして、思い出したように唇を開いた。
「スニオン・ロック」
カノンの肩が揺れた。
「あなたが組んだ特殊プログラムです。作動させると強制スリープモードに移行し、位置情報を含めた外部干渉を完全に遮断できる。おかげで我々はこの十三年間、ただの一度もあなたの消息を掴めなかった」
カノンへと向き直ると、ムウはその姿を正面からひたと見据える。一瞬だけ揺らいだかのように見えたカノンの体勢は、すでに立て直されていた。
「だが当然リスクもある。スリープ中の電源供給は、内部バッテリーに頼るのみ。しかしそれもいずれは尽きます。そうなる前にあなたは目覚めなければならなかった。スニオン・ロックの作動は、あなたの身を守るのと同時に、二度と起動出来なくなる危険性をはらんでいた」
ほんの少し前まで二人の頬をそよいでいた風が、今はぴたりと止んで、まるで空気が息を止めているかのようだった。ムウの顔からは、いつの間にか笑みが消えていた。
「いかな高性能モデルといえども、十三年もの月日を内部バッテリーだけでまかなえるはずがありません。つまりあなたには、スリープ状態から目覚めるだけのパワーは残されていなかった」
夜の闇に沈黙が落ちる。
「あなたは、なぜ今、このタイミングで目覚めることができたのでしょうか」
二人の周りは相変わらず、台風の目の中心にいるような静けさだった。
カノンは黙って話の行方を見守っているように見えた。核心に触れることは難しいだろう。だが、必ずしもすじ違いなことを言っているわけではないことも、ムウにはわかっていた。なぜならば、あれだけ饒舌にムウを煽って見せたカノンが、今はこんなにも長いこと口をつぐんでいるのだから。
「まあ、今は詮索しても仕方のないことです」
一変して気のないふうに告げると、ムウは雰囲気を幾分和らげた。下手に刺激して、必要以上に警戒心を煽るべきではない。契約主を得たとはいえ、依然として、カノンが危険なアンドロイドであることに変わりはないのだ。
「最後にひとつ、忠告しておくことがあります。ご存知の通り、今の私はめぞんゴールドの管理人。あなた方に干渉しないとは言いましたが、敷地内で面倒ごとを起こされれば話は別です」
すっと空気が冷える。
「これは、大家としての、私の権限です」
肝に銘じておいてくださいね、と付け加え、ムウは今度こそカノンに背を向けた。その後ろ姿が闇に紛れて消えるまでを見送って、気配が完全にたたれたのを確認してから、カノンは小さく息をついた。
ムウの推測は恐らく正しいのだろう。十三年の月日はあまりにも長すぎた。カノンが目覚めるのが先か、内部バッテリーの寿命が尽きるのが先か。そんなことはあの時点で誰にもわかりはしない。それでもカノンは一か八かの賭に出た。欠陥品と蔑まれ、飼い殺しのままやがて機能停止する日を待つのと、永遠の眠りにつくのとでは、一体どちらがましか。この場合、カノンにとって重要なのは、自分で選び取るという行為そのものだったのかもしれない。いずれにせよ、あの時のカノンに他の選択肢は残されていなかった。
そして今、結果としてカノンは目覚めた。
『あなたは、なぜ今、このタイミングで目覚めることができたのでしょうか』
カノン自身にもはっきりとした理由は分からないのだ。だが――。
夜の大気を大きく吸い込んで、カノンはじっと虚空を見詰めた。無数の星々が集まる巨大な銀河は、今も昔も変わらずカノンの上に広がっている。生まれてからずっと不自由を強いられてきたカノンも、夜空を見上げて、流星に身を任せるときだけは自由になれた。瞬く星たちに紛れ、この銀河をたどっていけば、過去にも未来にも行けるような気がした。カノンの記憶装置のもっとも奥深くにしまわれている、はじまりの記憶。そのときもまた、カノンは星の下に在った。
はっきりと理由はわからない。だからそれは、予感としか言いようがない。
朧気なビジョンがたぐり寄せる一つの陰、あるいは、光。堰を切ったようにという表現がアンドロイドにも当てはまるのなら、まさにそんなふうな勢いで、カノンをがんじがらめにしようと黒い影を伸ばす、何か。
凪いだ風が、ふたたびカノンの頬を優しく撫でた。見上げた夜空は暗い群青色で、星座の判別がつかないほど、たくさんの星で埋め尽くされている。
「サガ……」
忘れ得ない、たったひとつの名。
上空では、星たちが囁きあうように、静かな瞬きを繰り返していた。